【収入保険】私の選択・加入者の声
「高齢だからこそ収入保険」
【茨城県小美玉市 上田 稔さん】

経営規模=蓮根3ヘクタール
蓮根栽培は、17歳から始め68年が経過。品種改良の登録も4品種持っている。
高齢であることから収入保険は必要ないと思っていたが、高齢であるからこそ必要であるとNOSAI職員に勧められ加入を決めました。
収入保険を加入したその年は蓮根が豊作で価格が暴落し収入が減少しましたが、幸いにも保険金を受け取ることができ大変助かりました。勧めていただいた職員には感謝しています。
これから孫が蓮根栽培を継続してくれる予定ですが、その際に収入保険が経営の支えになってくれることを期待しています。
「加入して本当に助かりました」
【茨城県大子町 齋藤 親志 さん】

経営規模=りんご150アール
アメリカ西海岸で2年間の農業研修を経て、平成19年、祖父のりんご園70アールを継いで就農し、今では150アールまで拡大、約30品種のりんごを栽培しています。
収入保険に加入して5年目の令和6年に高温障害や炭疽病、ひょう害などで、収穫量が大きく減少し、それに伴い収入も大幅ダウン。
しかし、NOSAIからの速やかな保険金支払によって収入を確保することが出来て本当に助かりました。多発する異常気象等の備えとして、収入保険に加入することは必須であると思います。
「収入保険に救われました」
【千葉県茂原市 島田 陽子 さん】
(NOSAI千葉広報紙(NOSAIちば No.17号) 令和6年秋号より要約)

経営規模=エダマメ6ヘクタール/キャベツ(秋冬・春)3ヘクタール/その他作物 2ヘクタール
令和5年に加入して1年目、早生のエダマメは生育が順調でしたが、その後の暑さで収穫が見込めず「つなぎ融資」を利用し、資材等の支払いに充てることができました。他の品目でこれから挽回しようと一念発起した矢先、9月に線状降水帯による豪雨により畑が浸水。キャベツや落花生が大打撃を受け、収穫が見込めない状況に陥りました。その年の収入は大幅に減収となりましたが、青色申告書類に基づく評価により早期に保険金を受け取ることができ、大変助かりました。
近年の気候変動により、いつ大災害が起きてもおかしくない中、収入保険は農業経営に欠かせない保険だと実感しました。
「生命保険と同じくらい必要」
【山梨県甲斐市 飯室 智陽 さん】
(NOSAI山梨広報紙(NOSAI No.34号) 令和6年秋号より要約)

経営規模=水稲100アール/ネギ20アール
収入保険は、農業仲間からの紹介で令和5年から加入。年々、暑くなり作物が作りづらい気候になるなか、農業を生業としているので生命保険と同じくらい必要だと思い加入を決めました。保険料には甲斐市から助成があるため個人負担は安いと思います。
また、収入保険は気象災害以外にも、自身のけがや病気で作業ができなくなってしまった時も補償してもらえるのは、心強いですよね。
令和5年は高温障害で水稲・ネギともに収量が半減、等級も下がってしまいました。
不安の中、NOSAI職員の方が丁寧に対応してくれ保険金を受け取ることができ、安心しました。令和6年は、田植え時期を調整し、出穂後の高温にあわないようしています。
「未来へつなぐ保険であれ」
【茨城県かすみがうら市 根本 修さん】
(NOSAIいばらき広域 「旧NOSAIみなみ」 広報紙2020年7月号より要約)

経営規模=れんこん470アール
収入保険は、補償の幅が広く病気やケガ等の他、為替変動での損失も補償対象ということで、今後、海外向け販売を検討していることから、為替リスクもカバーできることが加入の決め手となりました。過去に台風被害で大打撃を受けたこともありましたが、収入保険の補てんがあり助かりました。また、収入保険は設備投資や人材の育成などチャレンジをする時の決断の後押しもしてくれます。これからも農家のために営農リスクを軽減できる保険であり続けてほしいと思います。
「炭疽病で収穫量減少収入保険でカバー」
【茨城県水戸市 久野 和美さん】
(農業共済新聞 令和5年8月3週号より要約)

経営規模=イチゴ30アール
イチゴ生産は天候に左右されます。収入保険に入っていれば、大きな災害で収穫量が減った場合でも安心感があります。
2022年のシーズンには、定植時から糸状菌によって引き起こされる炭疽病が発生しました。収穫量が25%ほど減少しましたが、この病気で収入が下がった分を補償してもらえたので良かったです。
「経営安定のためにおすすめの保険です」
【栃木県大田原市鹿畑 椎名 健一さん】
(農業共済新聞 2024年(令和6年)9月4日 第3518号より要約)

経営規模=主食用米と飼料用米を合わせて約350アール/ネギ61アール
収入保険加入は2023年。
加入初年の積立金が多く保険料等が高額のため加入を見合わせていましたが、NOSAI職員の熱心な推進とわかりやすい説明のおかげで、納得して加入をすることができました。加入後1年目の夏に、連日の猛暑で栽培していたネギに高温障害が発生。成長が阻害され予定通り収穫できず減収となりました。栽培を続けていいのか不安もありましたが必要書類を提出してから1か月足らずで保険金を受け取ることができ、とても助かりました。人生はいつ何が起きるかわからない。先行き不透明な時代に、経営安定のためにおすすめの保険です。
「安心して経営するために」
【群馬県伊勢崎市 かがやきいちご園 代表 齋藤 大輝さん】
(NOSAIぐんま 広報紙「NOSAIぐんま No.42号」 2024年夏号より要約)

栽培作物=イチゴ
令和4年から青色申告を始め、今のところは想定していた以上に業績を伸ばせていますが、営農を続けていけば努力をしても防げない自然災害や、いちごの病気が蔓延して大きな減収になる可能性があります。
収入保険に加入することで、経営の不安を軽減することができるので、色々なことに挑戦できます。今後、規模を拡大する際にはその増収を見越して加入できることも魅力です。
「経営環境の変化に備えて」
【東京都清瀬市 小寺 良治さん】
(NOSAI東京 広報紙「NOSAI東京No.40」 2024年3月発行より要約)

栽培作物=野菜950アール(カブ、ホウレンソウ、ミズナなど)
ホウレンソウ、カブ、ミズナを1年通して栽培し、冬には里芋、人参も栽培しています。祖父や父が築き上げた年間の種まきパターンを基本として、前年の生育状況を加味して次年度の営農計画を立てています。
昨今の生産資材の高騰や気候の変化へ対策、また、将来的に経営判断を任せらてもらえるようになった時を見据え、新しい品目への挑戦など経営環境が変化した際の安心材料の一つにできると思い収入保険に加入しました。
「助け合いの精神で」
【東京都足立区 牛込 聖英さん 直希さん】
(NOSAI東京 加入者の声チラシより)

経営規模=野菜105アール(トマト、きゅうり、小松菜等)
子育ても一段落したので、趣味のバイクを再開しました。
バイクで事故を起こし、仕事が出来なくなって家族に迷惑をかけるかもしれない、そのようないざというときに収入を確保するため収入保険への加入を決めました。
収入保険は自分の備えとしても魅力的ですが、全国の農業者の助けになる「助け合い」の精神が反映されており、「加入者の声」を通して全国の農業者の役にたっていることがわかることも魅力的だと思います。
今後は、息子が就農したので親子3人で牛込農園の直売所を盛り上げていきます。
「経営者として、万が一の時に安心を」
【東京都江戸川区 草薙 昭広さん】
(NOSAI東京 加入者の声チラシより)

経営規模=野菜(小松菜)28アール
区画整理による営農状況の変更を経て経営者となり、農業収入に対する備えが必要になると感じました。
収入保険に加入した最大の理由は、けがや病気などの要因で経営が成り立たなくなるリスクに備えるためです。
農業収入が減少した時に補償があることは、大きな安心であり農業を続けるための後押しにもなります。心の支えとして、収入保険は魅力的です。
「収入保険の加入で安心の備えを」
【神奈川県座間市 若菜 成之さん】
(NOSAI神奈川 広報紙「きずな」43号より抜粋)

経営規模=水稲200アール/小麦150アール/大豆50アール/野菜10アール
令和4年から収入保険に加入。それまで加入していた農作物共済と畑作物共済から収入保険に移行した。加入の決め手は、様々なリスクに対して幅広く手厚い補償があること。特に、いつ起こるか分からない自身の病気やケガで農業ができなくなった時の備えが一番の決め手となった。「農業は一発勝負。作物には種まきなど、適期があり、もしその時期に病気やケガなどで入院して種まきが遅れてしまったら収穫は見込めない。そういった時の備えができるのは、大きな安心」と話す。
「収入保険で手間なく安心」
【山梨県笛吹市 久津間 登さん】
(NOSAI山梨 広報紙「NOSAI No.34号」 2024年秋号より要約)

経営規模=ブドウ61アール
令和4年に果樹共済から収入保険に移行しました。保険方式のみ8割補償で加入したので、掛金は果樹共済と同等くらいでした。加入するときは青色申告決算書のコピーを提出するだけで、忙しい収穫期に損害評価を受けなくていいので楽ですね。それでいて補償割合も果樹共済(7割)より高いのが魅力です。
加入したときに、農作業日誌の記載を求められますが、私は以前から誘引や摘粒、消毒等日々の作業を、作業日誌に細かく記録していたので負担はありませんでした。
加入した年に紫玉とブラックビートで晩腐病とえそ果病が発生。収入が28%減少し、保険金を受け取りました。そこまで収入が減るとは思わなかったので、保険金が出ると聞き安心しました。
「適切な補償額で支払いも早く本当に助かりました」
【千葉県八街市 (株)八街産直会 斉藤 僚次さん、斉藤 照夫さん】
(NOSAI千葉広報紙(NOSAIちば)2023年秋号より要約)

経営規模=ブロッコリー4.5ヘクタール/キャベツ2ヘクタール/ダイコン2ヘクタールなど
2019年の台風15号ではハウス20棟のうち半数が倒壊、ビニール破損を含め全体の9割が被害を受け作物に大きな影響が出ました。当時はまだ収入保険に加入していなかったため、銀行から融資を受けました。
2022年に収入保険に加入。野菜価格の相場安や作物の病気、外国人実習生のコロナのクラスター感染などの原因で、計画的収穫が不可能となり減収しました。初めての保険金は適切な補償額で、支払いも早く本当に助かりました。
多品目の野菜を時期をずらして栽培し危険分散を図っていますが、天災が一番怖いですね。多くの従業員を抱え法人経営をしているため、オールリスクに対応した保険は必須だと考え加入しています。
「もしも」というときに。気持ちに余裕
【群馬県みどり市 岩崎 康博さん】
(NOSAI群馬広報誌「NOSAIぐんま」2023年冬号より要約)

経営規模=ほうれん草120アール/なす40アール
平成26年の雪害で園芸施設に被害を受け、リスクについて考えるようになりました。自然災害だけでなく、価格の下落やケガなど、農業にはリスクが付き物です。被害に遭っても固定費などの支払いは常に発生します。
収入保険にはつなぎ融資もあるため、気持ちに余裕をもって営農ができるところが魅力です。
掛金や積立金は最大9回の分割ができるので、初年度の持ち出しで迷われている方も検討してみてはいかがでしょうか。
「自然災害に対し収入保険は営農上の重要な対策」
【群馬県高崎市 清水 忍さん】
(NOSAI群馬広報誌「NOSAIぐんま」2023年冬号より要約)
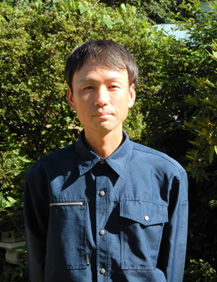
経営規模=プラム110アール/梨42アール
果樹営農の最大のリスクは自然災害です。技術力の向上や設備投資でリスクを減らす努力はできても、完全に回避することはできません。
果樹は、冬の剪定から長い期間をかけて秋の収穫を迎えますが、霜やひょうは一瞬にしてその景色を変え、営農意欲も奪ってしまいます。
保険金の支払いを受け、収入保険は営農上の重要な対策であるとともに、営農への気持ちを前向きにさせてくれる大きな存在だと感じました。
「雇用の安定化につながっている」
【群馬県前橋市 (株)上州農産 松村 徳崇さん】
(NOSAI群馬広報誌「NOSAIぐんま」2023年冬号より要約)

経営作物=大豆1,620アール/麦1,227アール
農業の規模を拡大している中、異常気象の多発や、外来植物の被害、大豆の湿害などの大きなリスクに備えることができる収入保険は、なくてはならない保険です。
また、無利子で「つなぎ融資」を受けることができるため、運転資金の心配を減らすことができ雇用の安定化にもつながっています。
安心して農業を続けていくことができ、とても心強いです。
「経営安定・従業員の雇用安定のための加入」
【群馬県嬬恋村 (有)ピュアウエーブ21 前田 康則さん】
(NOSAI群馬広報誌「NOSAIぐんま」2023年冬号より要約)

経営規模=キャベツ3,000アール
平成31年まで露地野菜には、経営全体を補償する保険制度がなかったため、経営安定や従業員の雇用を守るために加入しました。
加入した年には、価格低下やひょうによる被害に見舞われましたが収入保険の補償により、その後の経営の安定につながりました。
近年の異常気象など様々なリスクに備えるため収入保険は頼もしい存在です。
「ネギが病害により全滅の被害」
【埼玉県飯能市 (有)安藤農場 安藤 完二さん】
(NOSAI埼玉広報紙(NOSAIさいたま)2022年1月号より要約)

経営規模=ネギ、ダイコンなど5ヘクタール
農業収入全体をカバーできる点が魅力で、収入保険の開始後すぐに加入を決めました。
昨年は定植したネギ70アールが黒腐菌核病により全滅の被害を受けましたが、つなぎ融資を利用して農機具の維持費や種苗費、資材費に充てることができました。
今後も経営努力では回避の難しい事態が起きるかもしれません。多くの農業者の方へ収入保険の活用をおすすめします。
「想定外の収入減を補償」
【埼玉県美里町 大澤 清則さん】
(NOSAI埼玉広報紙(NOSAIさいたま)2023年1月号より要約)
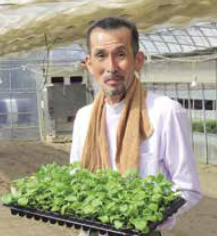
経営規模=切り花1ヘクタール
ハウス20棟と露地で、クジャクソウをメインに切り花を通年出荷しています。切り花生産の主なリスクは自然災害です。平成26年2月の大雪で園芸施設と栽培中のチューリップに損害を受けた経験から、雪や台風に備えて収入保険に加入しました。
新型コロナウイルスの影響で花の出荷量が減少し、収入が減少。全くの想定外でしたが、保険金で収入を確保することができました。
「フレキシブルにプラン設定が可能」
【東京都清瀬市 関 健一さん】
(NOSAI東京広報紙「NOSAI東京」2022年11月号より要約)

経営作物=トマト等90アール
養液栽培がメインであることから、病害虫や自然災害で減収したときに補償がしっかりと充実していることが加入した一番の決め手です。
各経営体によってフレキシブルに補償の上限・下限を選べることも魅力的なところです。
都市農業は農地の減少や宅地化が進む中で、年々とやりづらい環境になっていくと思いますが、小さな面積でもちゃんと農業経営ができるんだよと見本になるような農業経営をしていきたいです。
「補償の下限の設定が加入の決め手」
【山梨県北杜市 (有)アグリマインド 代表取締役社長 藤巻 公史さん】
(NOSAI山梨広報紙(NOSAI)2023年冬号より要約)

経営規模=ハウストマト2ヘクタール
セミクローズド型温室を導入し、トマトを生産しています。ココヤシ殻を培地にした養液栽培で、最先端技術によるコンピューター管理のもと、温度・換気量・CO₂温度等をコントロールしています。
それでもカバーできないリスクはあり、令和元年の台風15号では栽培を開始した矢先の千葉県に所有する施設が停電や浸水等で多大な損失を出しました。
収入保険は、自社では防げないリスクの部分を補償してくれる魅力的な制度です。法人だと基準収入が高くなりますが、補償の下限を設定することにより、保険料を抑えて加入することができたことも、加入の決め手です。
「コロナ禍で客激減」
【山梨県山梨市 (株)フルーツオーサー 代表取締役社長 大澤 澄人さん】
(NOSAI山梨広報紙「NOSAI」2023年冬号より要約)

経営規模=サクランボ1.5ヘクタール
山梨市でサクランボの観光農園を経営しています。サクランボは開花期の気温で結実が左右されるので豊作・不作の差が激しいです。経験上10年に1度は収入が落ちる年がありますが、山梨県ではサクランボの果樹共済を実施しておらず、収入保険ができたときは迷わず加入を決めました。
令和2年産は新型コロナウイルスの影響で例年1万人ほどだったお客様が500人に激減。他所への出荷や宅配も行いましたが、収入は3割ほど減収し、保険金を受け取りました。
従業員の給料や翌年の準備等もあるため本当に助かりました。
「不測の事態に備えて」
【埼玉県春日部市 相鴨飼育農場 倉常ファーム 代表 八木橋 喜一さん】
(NOSAI埼玉広報紙「NOSAIさいたま」2022年10月号より要約)

経営規模=アイガモ44,000羽/水稲8.1ヘクタールなど
アイガモは、孵化場から仕入れたチェリバレー種の雛を約8週間かけて肥育し、出荷しています。21年1月に雛の仕入先である孵化場で鳥インフルエンザが発生し、やむを得ず1300羽ほどが殺処分となりました。
本農場への感染はありませんでしたが、孵化場の雛再出荷には6か月を要し、その間は全く養鴨ができず大幅な収入減となりました。しかし、つなぎ融資を利用し、肥育再開に備えることができました。
衛生面に細心の注意を払っていても、経営努力では避けられないリスクに対して備える重要性を再確認しました。加入していて本当によかったと思います。
「新しい技術にも挑戦できる」
【山梨県市川三郷町 渡邊 千雪さん】
(NOSAI山梨広報紙「NOSAI」2022年秋号より要約)

経営規模=スイートコーン90アール/ニンジン13アール
令和元年から収入保険に加入しています。その年に、甘々娘が4月の遅霜に当たり、大塚ニンジンも高温で雨量が少なかったため発芽が悪く減収。補てん金を受け取りました。
多品目栽培でリスク分散している農家もいますが、昨今の気象変動では何があるかわかりません。保険料は経費として計上できるので、万一のために加入していたほうがいいと感じています。
スイートコーンの作業の省力化を図るために、トンネルの資材にパンチフィルムを使うなど、新しい資材や技術の導入などを積極的に行っています。収入保険に入っているからこそ、安心して挑戦できます。
「キャベツの価格低下を補てん」
【千葉県銚子市 横田 一裕さん】
(NOSAI千葉広報紙「NOSAIちば」2022年10月24日より要約)

経営規模=春キャベツ4ヘクタール/トウモロコシ1ヘクタール
以前は野菜価格安定制度を利用していましたが、収入減少の補償を受けられる収入保険に魅力を感じ、制度開始直後から加入しました。
昨年は天候に恵まれ春キャベツが豊作だったため、販売価格が例年の8割ほどに低下してしまいました。満額加入で備えていたため保険金の支払い対象となり、助かりました。
加入当時は新しい制度だったため不安もあり、近所の農家やJA職員にたくさん相談しました。最終的には公認会計士の方に「経営に合っているのは収入保険だ」と後押しをもらい加入を決断しました。
ブランド野菜「春潮キャベツ」の栽培にも挑戦しており、これからも良い野菜を作っていきたいです。
「規模拡大していたところに米価下落」
【栃木県那須塩原市 齋藤 勲さん】
(NOSAIとちぎ広報誌「NOSAIとちぎ」2022年夏号より要約)

経営規模=水稲40ヘクタール
収入保険は農水省ホームページの説明動画「しゅうほちゃんシリーズ」を見て、理解を深めたうえで加入しました。決め手は無利子のつなぎ融資です。収入減少が見込まれる場合に申請することができますが、肥料や資材といった経費の支払い期限が迫る中、申請から1か月で資金を受けることができて助かりました。
令和3年度は規模拡大をしていたところに米価の急激な下落があり、備えの大切さを実感しました。収入保険の加入は農業経営のお守りですね。
「規模拡大する上で必要な保険」
【栃木県真岡市 菅谷 拓夫さん】
(NOSAIとちぎ広報誌「NOSAIとちぎ」2022年夏号より要約)

経営規模=ネギ22ヘクタール/人参7ヘクタール/キャベツ7ヘクタール/水稲16ヘクタール
10年前に就農してから年々経営規模を拡大しており、従業員や設備投資も増えていたので、経営の安定を図るために令和2年に加入しました。規模拡大特例が適用できたので、充実した補償額で加入することができました。令和3年産は、主力のネギで軟腐病やハモグリバエによる食害により品質と収量が低下しました。また価格低下もあり大きな減収となりました。
経営規模を拡大するためには、雇用や設備の拡大をしなければなりません。収入保険に加入することで、減収があっても経費や設備投資の資金を担保することができ、安心して営農していくことができます。
「収入上昇傾向特例で補償額にも満足」
【栃木県那須烏山市 渡邉 拓美さん】
(NOSAIとちぎ広報誌「NOSAIとちぎ」2022年夏号より要約)

経営規模=水稲65アール/ナシ144アール
令和3年産は4月に2度の降霜があり、ナシが大打撃を受けました。過去一番の被害だったので収入保険に加入していてよかったと心から安堵しています。
基準収入は収入上昇傾向特例が適用されたため、過去に大きく減収した年があっても、平年並みの金額で加入することができ、補償額にも満足しています。
営農経費の支払いなど出費が多い年でしたが、必要書類を提出後、1か月足らずで補てん金を受け取ることができ、とても助かりました。
「けがで収入減少」
【埼玉県鴻巣市 飯塚 和彦さん】
(NOSAI埼玉広報紙「NOSAIさいたま」2022年7月号より要約)

経営規模=花苗ハウス52アール
オリジナル品種「フクシア・ルージュブラン」をはじめ10品種以上を栽培しています。2021年はけがの多い年で、立て続けに足と腕を骨折し、入院に加え半年の車いす生活を余儀なくされました。
作業全般ができず、コロナ禍も相まって収入が減少しました。人件費や資材費の支払いが心配でしたが、つなぎ融資を利用し補うことができました。支払いまでが素早く、無利子で借りられたのでとても助かりました。
無事、春の植え付けができ、加入していてよかったと実感しています。
「春先の凍霜害などで収入が半分に 次年も予定通りの営農ができた」
【栃木県宇都宮市御幸町 監物 瑛さん】
(NOSAIとちぎ広報誌「NOSAIとちぎ」2021年夏号より要約)

経営規模=ナシ3ヘクタール
制度を最初に聞いたとき、手厚い補償に対し保険料等がこんなに安くていいのかと、とても驚きました。
ナシはその年の天候や市場価格の変動に左右されます。令和2年度は春先の凍霜害と長梅雨で収入が半分近く落ち込みました。しかし保険金等のおかげでほぼ通常の収入に戻り、令和3年度は予定通りの営農ができました。
毎年の収入の凹凸を平らにしてくれるので、天気や価格の影響を受けやすい果樹農家には特におすすめです。
「保険に加入している安心感」
【山梨県北杜市 高松 拓さん、百合佳さん】
(NOSAI山梨広報紙「NOSAI」2021年秋号より要約)

経営規模=露地野菜200アール/ハウス3棟
ナス、キュウリ、玉ネギ、トマト、ピーマン、人参、大根、カブ、ブロッコリー、葉物野菜など年間を通して栽培しています。
先輩農家に勧められ、2021年から収入保険に加入しました。多品目で危険分散はしていますが、有機栽培だと病害や天候により収穫量が安定しません。収入保険に加入していることで安心感があります。
「病気で入院 収穫できないリスクへの備え」
【東京都日野市 和田 洋介さん】
(NOSAI東京職員インタビューより作成)

経営規模=トマト等83アール/ブルーベリー43アール
昨年病気になり、平成31年3月から農業を約3か月休むことになりました。
トマトの収穫時期と重なり収入に不安を感じていましたが、収入保険に加入していたおかげでしっかりと治療に専念することができ、現在は体調も回復し農業に専念できるようになりました。
トマトの収穫ができなかった分の収入が補てんされるので大変助かりました。
「営農計画に見合った収入を補償してくれることに魅力」
【山梨県北杜市 そらくも農場 鈴木 啓志さん(51)】
(NOSAI山梨広報紙「やまなしNOSAI」2021年秋号より抜すい)

経営規模=水稲150アール/大豆70アール/ハウス野菜13アール/露地野菜30アールほか
農薬不使用や、減農薬で栽培しているので、異常気象で何かあってもすぐに農薬で抑えることはできません。昨年は新型コロナの影響で道の駅が休業したり、妻が病気になったりもしました。
収入保険については、毎年栽培面積が増えていて営農計画を変えているので、過去の平均収入の補償では実情に合わないなと思っていましたが、「規模拡大特例」を使うことで、規模拡大後の営農計画に見合った補償で加入できることを知りました。収入保険は、本当に自分の望んでいた補償内容でした。
「イチゴの病害やビール麦の収量減、水稲の価格下落の影響による収入減の支えに」
【栃木県小山市 遠井農園 遠井 尚徳さん(40歳)】
(NOSAIとちぎ広報紙「NOSAIとちぎ」2021年夏号より抜すい)

経営規模=水稲11ヘクタール(主食用7ヘクタール、飼料用4ヘクタール)/二条大麦15ヘクタール/イチゴ90アール
令和2年は、イチゴに病害が発生し、収量がかなり減収しました。更にビール麦の減収や水稲の価格下落も重なり、全体的に大きく収入減少した年でした。
収入が減っても薬剤費や人件費等の固定費の支払いがあるため、無利子のつなぎ融資を申請しました。申請から約1か月で支払われ、思っていたよりも多い金額だったので、経費の支払いに充てることができ大変助かりました。
収入が安定することで心にゆとりができ、新しいことにもチャレンジできるのも収入保険に加入しているメリットの一つですね。
「天候不順や新型コロナウイルスの影響による収入減を補てん」
【栃木県那須塩原市 手塚 一清さん(53)】
(NOSAIとちぎ広報紙「NOSAIとちぎ」2021年夏号より抜すい)

栽培規模=水稲6ヘクタール、ハウストマト40アール/ハウスキュウリ28アール/ブロッコリー(春秋)90アール
経営や収入の安定を考えて、収入保険に加入しました。補てん方式に迷いましたが、仲間と相談し、掛捨ての「保険方式」に掛捨てでない「積立方式」を組み合わせた補償を選択しました。
昨年は、メイン収入であるトマトやブロッコリーが天候不順により減少しました。また、新型コロナウイルスの影響で取引先への出荷量も減少しました。ここまで売り上げが伸びてきていたところでしたので、収入上昇傾向特例を活用できたことも良かったです。保険金等の支払いが早く、借り入れせずに乗り切ることができ、大変助かりました。
「新型コロナウイルス感染症による休校や取引先の撤退の影響による収入減の支えに」
【栃木県高根沢町 小西 美好さん(46歳)】
(NOSAIとちぎ広報紙「NOSAIとちぎ」2020年秋号より抜すい)

経営規模=菌床なめこ約4万個
きのこ類には保険制度がなかったため、長年不安定な環境で営農していました。収入保険は収入ベースの補償なので分かりやすく、まさに待ち望んでいた制度です。
新型コロナウイルス感染症による休校や取引先の撤退で、半年近く出荷が滞る状況が続いたので、つなぎ融資の申請をしました。申請後はすぐに融資が下り、運転資金に充てることで作物転換や廃業を視野に入れずに済んでいます。
加入していることで余裕も生まれ、販路拡大など「攻めの農業」を考えるゆとりもできました。
「怪我で作業ができない期間の支えに」
【千葉県館山市 杉田 恒雄さん(71)】
(NOSAI千葉広報紙「NOSAIちば」2020年秋号より抜すい)

経営規模=イチゴ(とちおとめ、かおりの、やよいひめ)20アール/水稲160アール
昨年9月の台風15号で、南房総地域は特に甚大な被害を受けました。
倒れたイチゴのハウスを1週間後の定植に向けて片付けをしていたとき、足の怪我(アキレス腱断裂)をしてしまいました。
収入保険は、怪我で作業が出来なくなり収入に影響が出たときも補償してくれるので有り難かったです。
つなぎ融資は申請が簡単で、NOSAI職員へ話してから1か月程で入金され、助かりました。
これからも健康に気を付けて、1日でも長く農作業をやっていきたいです。
「台風による被害を補てん」
【神奈川県開成町 宮上 透さん(32)】
(農業共済新聞[首都圏版]2020年8月4週号より)

栽培規模=オクラ15アール/サトイモ90アール/スイートコーン55アール/露地野菜90アールほか
初年度から収入保険に加入し、毎年経営面積を広げてきましたが、昨年の台風15号・19号の影響で、収穫予定だった作物が打撃を受けました。
規模を拡大する上で必要経費はかさんでおり、運転資金が不足することは明らかでしたが、規模拡大特例が適用された基準収入が設定されていたことで、収入保険の補てん金が支払われ、今年の春に必要な肥料や農薬、マルチなど生産資材の購入代金を賄うことができました。
規模拡大特例で、保険金額を平均収入よりも多く設定できたおかげです。経営基盤が整う前の若手農家にとって心強い制度です。
「収入保険は農家の心強いパートナー」
【栃木県佐野市 青村 章さん(70)】
(NOSAIとちぎの担当職員によるインタビュー)

栽培規模=水稲15ヘクタール
私の住む地域は比較的災害の少ない場所でしたが、収入保険にはケガや病気で耕作できない場合に備えて加入していました。
令和元年10月に発生した台風19号で収穫前の耕地が水没しました。被害の状況を見たときは言葉を失いましたが、保険金の請求手続きをしたところ、すぐに支払ってくれたので、今年も変わりなく営農することができます。加入していて本当によかったです。
最近は毎年のように異常災害が発生しています。これからの時代、収入保険は無くてはならない「農家の心強いパートナー」です。
「安心経営には“備え”が必要」
【神奈川県相模原市 有限会社内藤農産 代表 内藤 光夫さん(68)】
(NOSAI神奈川広報紙「きずな」37号より抜すい)

栽培規模=大豆2.7ヘクタール/ブルーベリー10アール/カキ10アール/露地野菜30アール
ブランド展開で独自の価格設定をしている農産物があるので、販売収入全体が補償の対象になる収入保険に魅力を感じ、加入を決めました。
また、農業共済の対象ではない果樹の品目や露地野菜が補償の対象になるのも魅力ですね。
昨年は、妻が体調を崩して入院してしまいました。家族経営の場合、人員不足は経営にも影響が出ます。このような経営努力しても避けられない、病気やけがなどの様々なリスクがあるため、収入保険を安心して農業経営できる“備え”にしたいと思っています。
「幅広い補償が魅力」
【神奈川県伊勢原市 片野 泉さん(59)】
(NOSAI神奈川広報紙「きずな」37号より抜すい)

栽培規模=水稲1.7ヘクタール/トマト15アール/露地野菜30アール
自然災害だけでなく、けがや病気などで収入減少した場合でも補償対象になるので加入を決めました。
また、数年前に田植機を整備していたときに右腕を負傷し、夏野菜の栽培ができず収入が大幅に減少した経験があるのですが、NOSAI職員の方から収入保険の説明を聞いたら、すぐに加入しようと思いましたね。
今は自分のことは自分で守らばければいけない時代です。農家のために作ってくれた制度を上手に活用していきたいです。
収入保険は新たな品目に挑戦する場合や、規模拡大をする場合など農業においてチャレンジしたい人には特に魅力的だと思います。何かあったときのためにも、興味がある人は早めの検討をおすすめします。
「自然災害に備えられる安心感」
【東京都国立市 佐藤 英明さん】
(NOSAI東京広報紙「NOSAI東京広報」 No.17より)

経営規模=梨30アール/野菜等50アール
収入保険は、NOSAI東京の職員から最初に説明を受けた時に、とても良い制度だと感じました。農林水産省の説明会にも参加して加入するしかないと確信に変わり、すぐに加入を決めました。
積立金の75%が国庫補助で、補償割合が最大90%という手厚い制度を考えると掛金は割安であると感じています。
果樹農家としては自然災害に備えられるのは非常に安心感があります。全国的にも自然災害が大規模化する傾向にある中で、今年5月の雹害は国立市では40年ぶりの規模で、私の梨園も大打撃を受けました。収入保険に加入しておいて本当に良かったと思いました。こんなに良い制度は他に無いと思うので、より多くの方に利用してもらえたら良いと思います。
「不測の事態に備えることが大切!」
【群馬県高崎市 佐藤 健さん(42)】
(NOSAIぐんま広報紙「NOSAIぐんま」2019年VOL.33より)

兼業農業でうめを栽培しています。
妻と小学生の子供がいるので、けがや病気で作業ができなかった場合の収入減少が心配で加入を決めました。
今年は数十年に一度といわれる降雹がありました。やはり不測の事態に備えることは大切だと思います。
今後は新しい作物の栽培も検討しています。初めて挑戦する品目も収入保険は対象ですから安心ですね。
「従業員への責任」
【群馬県利根郡みなかみ町 本多 圭仁さん】
(NOSAIぐんま広報紙「NOSAIぐんま」2019年VOL.33より)

りんごやブルーベリーなどの果樹中心ですが、そばや水稲、野菜など多品目を栽培しています。
家族だけでなく従業員の雇用を守る責任があるので、収入保険に加入しました。
果樹共済の特定危険方式に加入していましたが、この方式が廃止されることもあって、収入保険へ切り替えました。
農業は天候等に左右されるため、収入が安定するとは限りません。何かあってからでは遅いので、収入保険は非常に良い制度だと思います。
「農業は身体が資本!」
【群馬県伊勢崎市 赤石 和之さん】
(NOSAIぐんま広報紙「NOSAIぐんま」2019年VOL.33より)

なすとほうれんそうを栽培しています。
人生にはまさかの「坂」があります。農業は天候に左右され、毎年同じようにはいきません。最盛期には3ヵ月程度休みがないなど体力勝負なため、万が一の際も収入保険は安心できます。
「加入はまだ様子を見て」という方もいると思いますが、被害がなければ掛金も下がるし、安定してるからこそ加入するという選択もありだと思います。
「法人には大変魅力のある保険!」
【群馬県館林市(有)多々良フレッシュファーム 小林 幸枝さん、滝野瀬 雅彦さん】
(NOSAIぐんま広報紙「NOSAIぐんま」2019年VOL.33より)

いちご、水稲、麦、野菜を栽培しています。
いちご狩り(観光農園)の入園料も、税申告上、農産物の販売金額に整理しており、保険の対象収入に含まれたことに魅力を感じました。
いちご栽培のほか、米麦や野菜を多品目栽培していますが、野菜価格安定対策の対象でなかったものも数多く栽培しているので、収入保険は大変魅力です。
農業法人の事業としてやっているので、全体の売上げを補償してくれるのはありがたいですね。
「つなぎ融資があり、助かりました」
【埼玉県久喜市 株式会社CTIフロンティア 取締役 野村 奏史さん(41)】
(NOSAI埼玉広報紙「NOSAIさいたま」2019年10月号より)

私たちは、久喜市を中心に10ヘクタールの農地を借り、レタスやキャベツなど数十種類の野菜を露地やハウスで栽培しています。
5月の降雹、7月の日照不足、8月の高温により、露地の主力農作物数種類に大きな被害を受けました。これにより、売上の大幅な減少が見込まれたため、秋冬作のことも考え、「つなぎ融資」を希望しました。
保険ができてまだ間もないので実際に支払われるか不安でしたが、手続きは簡単でスムーズ、申請してからおよそ1か月で支払われ助かりました。
今後は、収人保険へ加入したことで、資金繰りに悩むことなく次回作の見通しや翌年の計画が立ち、経営の幅を広げることができます。
「価格変動に頼もしい備え」
【栃木県鹿沼市 (株)コバヤシファーム 代表取締役社長 小林 哲哉さん(42)】
(農業共済新聞[北関東版]2019年10月1週号より抜すい)

栽培規模=ホウレンソウ10ヘクタール、コマツナ40ヘクタール
農業収入全体をカバーする、どの保険会社にもない商品です。茨城県や群馬県の仲間にも制度を勧めています。
露地野菜は自然災害を受けやすく、 2013年に竜巻、2014年に雪害、2015年に水害を受けた苦い経験があります。作物を問わずに加入できるのはありがたいです。
スーパーとは価格固定で契約していますが、今年のように生育が順調だと市場が飽和状態になり、価格が低迷し、注文数が減少します。こうした価格変動に備えられるのも大きいですね。
地域が高齢化していく中、委託される圃場の数も増えますが、その農地の良し悪しは作付してみないと分かりません。こういったリスクがあっても、加入していれば、リスクを恐れずに挑戦できます。
「けがや病気のときも安心」
【山梨県笛吹市 雨宮 美武さん(37)】
(農業共済新聞2019年9月4週号より抜すい)

両親、妻と4人で、1.7ヘクタールほどで、「日川白鳳」と「浅間白桃」を主力に、「はなよめ」「一宮白桃」「黄金桃」など多品種を栽培しています。
加入の決め手は、けがや病気による収入減少が補償の対象になることです。万一のとき、誰かに管理を頼もうにも、みんな同じ時期に忙しいので、難しいかもしれません。
また、私たちの地域では、今年の5月にひょうが降り、かなりの被害が発生しました。自然災害のリスクは高まっていると思います。
市場価格の低下による収入減少も補償対象になるのは、収入保険の大きな魅力ですね。掛金は、補償される範囲を考えれば、高くはないと思います。
収入保険に興味がある仲間から「加入してみてどうだった?」などと聞かれることがあります。私としては、被害・事故の有無にかかわらず、収入保険に加入していることで安心して仕事に取り組めたことが大きかったと感じています。
「収入の減少が補償対象」
【茨城県大子町 佐川 明宏さん(50)】
(農業共済新聞[北関東版]2019年10月1週号より抜すい)

1.5ヘクタールで50品種近くのリンゴを栽培し、観光リンゴ園を経営しています。ほぼ全量を果樹園で販売しています。
過去に降ひょう被害や台風被害を受けたこともあり、更に中山間地域のため、イノシシによる苗木や下枝の被害も多く、心配は尽きません。
私の地域では、リンゴを対象としたセーフティネットがなかったので、品目に関係なく農業収入の減少を補償する保険はありがたいです。市場価格ではなく自分の販売金額で補償することや、無利子のつなぎ融資があることも魅力ですね。
現在、山形県で農業研修中の息子が、来年、後継者として戻ってくるのを機に、新規作物としてブドウを栽培し、危険分散を図りたいと思います。
新規作物チャレンジへのリスク回避と、何よりも「息子に安定した農業経営をさせたい」という思いがあり、加入しました。
「安心して農業経営に挑めます」
【茨城県筑西市 遠藤 純也さん(44)】
(NOSAI茨西広報紙「いばにし」2019年4月号より)
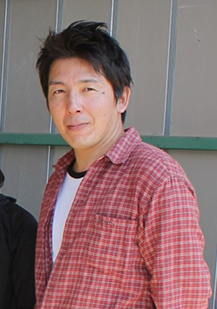
水稲、麦、大豆、そばの経営を行っています。3年前に義父が病気を患い、それを機に妻と共に就農しました。現在、亡くなった義父の遺志を継ぎ、義母を含めた3人で農業を行っています。
就農間もない期間で義父が亡くなったため、当初は残された家族で手探りの状態でした。周囲の方からの協力も得ながら、1年、また1年と季節を繰り返し、農業の知識や経験を積み重ねています。
新たにスタートした収入保険については、義父も生前、このような制度ができた際には加入したいと話していました。義父から引き継いだものを守りながら、さらに営農規模の拡大も目指したいと考えています。販売収入が補償される収入保険に加入した事で、安心して積極的な農業経営に挑むことができます。
「どうしようもできない被害への対策に」
【茨城県古河市 株式会社内田農園 代表 内田 信一さん(62)】
(NOSAI茨西広報紙「いばにし」2019年6月号より)
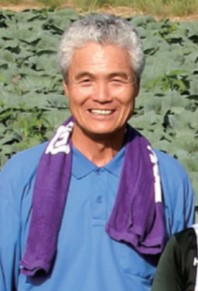
キャベツ、レタス、生姜など野菜を中心に栽培しています。
私と妻と娘夫婦の4人を中心に収穫から出荷、集荷や事務処理などを行っています。収穫及び集出荷作業は、従業員7名と野菜を納品している取引先から農作業の経験をするために来ている社員(入社1、2年目)4名、ラオスからの研修生8名で行っています。
新たにスタートした収入保険については、特に農業は自然との戦いであり、天候は自分ではどうしようもできないことなので、対策として収入減少を補える収入保険への加入を決めました。
組合には今まで以上にPRしてもらい、将来的には、認定農業者が収入保険に加入するのが当たり前となるような制度になってほしいですね。
将来は、ハウスの拡張を含め規模拡大を行い、一歩先を見据えた経営をしたいです。
「補償範囲が広く安心」
【茨城県下妻市 若本 智さん(55)、夏美さん】
(NOSAI茨西広報紙「いばにし」2019年10月号より)

梨栽培の師匠でもある父と妻の3人で「幸水」、「豊水」、「あきづき」、「新高」のほか、まだ出荷はしていませんが茨城県オリジナルの新品種である「恵水」を加え2ヘクタール程を栽培しています。
今年は、黒星病、みつ症状などの病気や、台風の影響による落果もあり、収入への影響が懸念されますが、収入保険に加入しているので、今までの果樹共済に比べ補償が大きく、気分的にも楽になり安心していられますね。
妻は、家事と子育てをしながら農業も頑張ってくれて、とても感謝しています。今後も、家族で頑張れる現在の規模を維持していきたいと思っています。
「日々のデータ管理で手続きスムーズに」
【山梨県北杜市 坂本 貴司さん(43)】
(NOSAI山梨広報紙「NOSAIやまなし」2019年7月号より抜すい)

経営規模=約2ヘクタールで有機野菜(露地野菜30品目)
昨年11月頃に、NOSAI職員の長坂さんから「野菜の補償は今までなかったので、ぜひ坂本さんにおすすめしたい。」と連絡をいただき、収入保険の説明を伺いました。
野菜は米などと違って、畑をまわしながら年間の作業を行います。特に苗を作る春先に長期で休むと、その年の収入がほとんどなくなってしまうので、以前から不安はありました。収入保険では、けがや病気で収穫ができない場合でも、年間収入が補償される点がいいですね。
多品目栽培ですが、販売金額や栽培面積、作業日誌はすべてパソコンで管理しているので、加入申請手続きに問題はありませんでした。地域の平均単価ではなく、実際の販売単価で基準収入を算定できました。
補償される金額に対して、保険料等は安いと感じました。収入がゼロだった場合でも、基準収入の8割以上が補てんされるわけですからね。
「収入保険で万が一に備える」
【埼玉県狭山市 松井 克実さん(50)、次女 由佳さん】
(NOSAI埼玉広報紙「NOSAIさいたま」2019年7月号より抜すい)

25年ほど、本格的に農業に取り組んでいます。米、麦、大豆を栽培しており、今年から次女が主体となり、新たにネギの栽培を始めました。
収入保険では決算書の数字を使うので、実際に支払われる保険金が目に見えて分かりやすいこと、また作物ごとに個別で加入するのではなく経営全体で加入できることも魅力だと思います。掛金がすべて掛け捨てではなく、積立部分があることも良いですね。周りの農家を見ても、大規模の農家は収入保険の加入に意欲的だったと感じました。
今のところ被害はなく、保険は使わないようにできることが一番ですが、なにがあるか分からないので備えて安心したいと思っています。
「農業を守る収入保険に期待!」
【埼玉県熊谷市 新井 清澄さん(71)】
(NOSAI埼玉広報紙「NOSAIさいたま」2019年7月号より抜すい)

主食用米12ヘクタール、飼料用米3.7ヘクタール、小麦5.6ヘクタール、二条大麦7ヘクタールを栽培しています。
私の暮らす地域は自然災害が少ないのですが、事故や病気で動けなくなった経験から、万が一に備えるという気持ちで、以前から共済制度に加入していました。収入保険への加入の決め手は、NOSAI職員の方に他制度と比較した掛金や補てん金の算定シミュレーションをしていただき、収入保険の方がより魅力的だったことです。
価格の低下や保管中の事故など今までは補償できなかった部分が補償されることや、ほぼすべての作物が対象となっていること、農家収入全体をひとつとして加入できることがメリットだと感じています。特に複数品目を栽培している農家には最適な保険だと思い、知人の野菜農家にも加入を勧めました。
「リスク回避により安定した農業経営へ」
【埼玉県行田市 (株)O・いしいファーム 代表取締役 石井 幸壽さん(70)】
(NOSAI埼玉広報紙「NOSAIさいたま」2019年7月号より抜すい)

水稲18ヘクタール、麦類10ヘクタールと米麦中心の経営を行っています。収入保険は、農業経営をしていくうえで、突発的な事故やゲリラ豪雨のような予想を超える自然災害に対応できる保険だと思い、いち早く加入を決めました。
経営管理は、20年程前からソリマチの農業簿記のソフトを利用して、常に費用対効果を意識しながらPC上で経営分析をしています。収入保険は、今後の農業経営に必要不可欠な制度だと感じており、減収時の補償に大いに期待しています。また、地元の農家から税申告の相談を受けることが多く、収入保険に興味がある農家にはNOSAIへ相談するよう勧めようと思っています。
「病気やけがも経営リスク」
【群馬県高崎市 ゆあさ農園 代表 湯浅 直樹さん(61)】
(農業共済新聞2019年7月2週号より抜すい)

ウメ1.35ヘクタールなどを栽培し、生ウメ、梅干し、練り梅、梅酢や梅粉を販売しています。販路は都内を中心とした企業や全国の個人です。また、先日、JETRO(日本貿易振興機構)を通じて、フランスへ梅干しを初輸出しました。
農業経営には、ひょう害で傷による不良率の増加や、企業との取引の急な取りやめ、原発事故によるシイタケ栽培の廃業やウメの販売先の減少など様々なリスクがあります。
収入保険に加入する最大の理由は、万が一のけがや病気で作業できない場合のリスクに備えるためです。基本的に夫婦2人だけの作業なので体調不良には不安があります。
また、近隣で農作業事故があり、傾斜地での農作業は、どうしても危険を感じる場面があります。もしも、夫妻どちらかが作業できなくなって、1年間販売が落ち込んでも、補償さえあれば、経営が継続できると考えています。
農業はいつ何があるか分かりません。保険に入っておくことは大前提だと思います。
「収入保険に期待したい」
【群馬県桐生市 山口 忠幸さん(46)】
(「NOSAIぐんま」 2019年VOL.30より)

農林大学校卒業後、父の元などで12年間修業し、32歳の時に独立しました。現在は、自分と妻、母、パートさんの4名でナスを栽培しています。
最初は失敗も多くありましたが、家族や地域の人の協力により、年々規模を拡大しながらここまでやってこれました。この感謝の気持ちは常に忘れません。2人の息子たちも農業に興味があるようで、いつか一緒にできたらと夢を膨らませています。
平成26年の大雪によりハウスが倒壊し、収入が無くなるという大変な思いをしたことから、1月から始まる収入保険に加入しました。また、ハウス本体は園芸施設共済にも加入することで、様々な事態に備えています。収入保険や共済制度が農家のセーフティネットとなるように期待しています。


