【収入保険】私の選択・加入者の声
「安心して品質の良いもの作るために」
【北海道釧路市 有限会社石井農園 代表取締役 石井 悟 さん】
(NOSAI北海道広報紙(NOSAIほっかいどう No.17号) 令和7年3号より要約)

経営規模=ダイコンなど 約19ヘクタール/ハウス野菜(ホウレンソウ、トマト、ピーマンなど) 35棟
実家の家業を継ぎ、就農した当初はホウレンソウのみの栽培でしたが、消費者の要望に応え栽培する作物を増やしてきました。栽培作物を増やしていく中で、いつ災害が発生するかわからないので、安心して作物を作りたいと思い、収入保険への加入を決めました。加入後に大雨による被害を受けた際には、早期につなぎ資金の貸付けを受けられたため非常に助かりました。
また、出荷のほか、自社の直売所でも野菜の販売をしています。家庭菜園が人気で自ら野菜を作る方も増えていますが、作る大変さも知ったうえで農家の野菜を買ってもらえるよう、「品質の良いもの」をモットーに消費者が安心して購入できる野菜作りを心掛けています。やりたいことは多々ありますが、身の丈に合った営農を行い、万が一のことがあれば収入保険に助けてもらいながら、いつかは息子に安心して継いでもらいたいと思っています。
「異常気象による収入減少への備え」
【青森県東通村 村田 睦夫 さん】
(NOSAI青森広報紙 「NOSAI AOMORI No.32号」 令和7年7月号より要約)

経営規模=イチゴ89アール(ハウス33棟)/ニンニク130アール
以前、高温が続いた年にハウス栽培のイチゴが影響を受け、出荷基準外の製品が多く大幅な収入減少となりました。その際、収入保険に加入していたため、保険金を受け取ることができ大変助かりました。
収入保険に加入していたことで、現在も面積を減らすことなく安心して農業経営を続けることができています。農家自身で作物の管理・栽培環境の整備に努めても、収入減少に繋がる様々な想定外の要因がありますので、収入保険に加入していない農業者の方には、今後の安心できる農業経営のためにも加入をおすすめします。
「収穫直前のスイカ水没」
【秋田県横手市 皆川 勝雄 さん】
(農業共済新聞「あきた版」令和7年6月3週号より要約)

経営規模=スイカ130アール/ホウレンソウ22.5アール/ミニカリフラワー20アール
以前は、野菜価格安定制度に加入していましたが、収入保険制度が発足した年に、補償の幅広さに魅力を感じ収入保険に切り替えました。
令和3年は、高温少雨でスイカの根が張らず収量が減少。保険金等が支払われ、翌年の経営安定につながりました。また、令和6年には、7月下旬の大雨で大玉スイカの圃場が冠水。設置していたポンプ3台を稼働しても排水が追い付かず、消毒を施しましたがつるが枯れてしまい通常の3分の1まで収量が減少。つなぎ融資を活用した上で保険金等を受け取ることができ助かりました。
今後は、これまでの被害により過去5年間の平均収入が下がってしまったことから、以前の平均収入まで早期に戻すことが目標です。
「つなぎ融資に助けられた」
【山形県酒田市 荒生 道博 さん】
(農業共済新聞 やまがた版 令和7年7号1週号より要約)

経営規模=水稲200アール/ネギ60アール/シイタケ3,200床
以前から「野菜なども含めた栽培品目すべてが対象の保険があれば」と思っており、近年多発する異常気象に備え、制度開始初年度から収入保険に加入しています。
令和6年7月の豪雨では、水田の約6割におよぶ範囲に土砂や流木が流れ込んだほか、ハウスや農機具も被災しました。収入の見通しが立たず、農機具や資材代の支払期日が迫る状況で「つなぎ融資」を利用し、無事に経費を支払うことができ、本当に助けられました。
被害が甚大だった川沿いの水田は、今もなお土砂や流木が残り、農地の復旧には最低でも3年はかかる見通しです。早期復旧に向けた取り組みを行うとともに、「制度の拡充のきっかけになれば」と自らの経験を発信しています。
「雇用を守れる安心感も」
【福島県南会津町 株式会社土っ子田島farm 代表取締役社長 湯田 浩和 さん】
(農業共済新聞[福島県版] 令和6年7月1週号より要約)

経営規模=花き71アール/アスパラガス25アール
令和2年の新型コロナウイルス感染症の影響で、花きの需要低下への不安を感じていた時、普及所の紹介で収入保険を知りました。価格低下のほか、けがや病気で人手不足となり収穫できない場合など、幅広く補償してくれると知り令和3年に加入しました。
実際その年に売り上げが大きく落ち込んでしまい、保険金を受け取ることができ、とても助かりました。
近年の異常気象や自然災害が多発する中、従業員の生活を守る立場としては、非常時に9割の収入が補償される収入保険は経営への安心感が非常に大きいです。
花きは数年でトレンドが変わり、新しい品種を栽培することがあります。そうしたチャレンジの際にも収入保険の存在が助けになっています。
「経営方針転換の後押しに」
【北海道北斗市 株式会社 畠山ファーム 代表取締役 畠山 誠さん】
(NOSAI北海道広報紙(NOSAIほっかいどう No.7号)2023年7月号より要約)

経営規模=長ネギ、水稲、ホウレンソウ、コマツナ、白カブ 約12ヘクタール
以前は、トマト栽培を収入の軸にしていましたが、法人化を見据え経営規模を拡大しようと考えていました。トマト栽培を拡大させるには、ビニールハウスを増築するための費用や収穫に要する人員の確保など多くの課題があり、ビニールハウスでの栽培に加えて、露地栽培が可能な長ネギへの転換をするとしても自然災害に対するリスクが高いことが懸念でした。
そんな中、収入保険制度がスタートするという話しを聞き、個人の過去の平均収入を基にして補償される点や、経営規模の拡大や収入が上昇したときにも対応ができる点に魅力を感じ加入を決めました。リスクへの対策が出来たことから、トマト栽培から長ネギ栽培への経営方針の転換を行い、目標だった経営規模の拡大と令和3年には法人化を行うことが出来ました。様々な特例や自然災害等が発生したときのつなぎ資金など、これからも農家のための制度であってほしいと思います。
「農業経営の基盤安定に」
【北海道江別市 保倉 浩行さん】
(NOSAI北海道広報紙(NOSAIほっかいどう No.10号) 2024年1月号より要約)

経営規模=水稲、小麦、レタス、子実用トウモロコシ 約20ヘクタール
元々、農業共済に加入していましたが、全国各地で異常気象による災害をメディアなどで見聞きすると、自分自身が被害を受けたときの経営の不安に駆られていました。その中で、NOSAIの地区担当職員に農業共済では補償の対象外となっていた価格低下での補償など、細やかな説明をしてもらい収入保険への加入を決めました。
加入した年は、自分自身は影響が少なかったですが、干ばつによる収量減少や新型コロナウイルスによる価格低下により収入への影響を受けた農家が多く、改めてもしもの備えが必要だと実感しました。近い将来、息子へ経営移譲をする予定なので安定した経営が引き継げるよう、営農に取り組んでいきたいし、近年の生産資材価格の高騰により所得は年々減少しているので、安定した営農を続けるためにも、今後は所得の減少を補償してくれる制度になってほしいと思います。
「人間なにかしらあるもの」
【青森県東北町 向井 博徳さん】
(NOSAI青森広報紙 「NOSAI AOMORI No.29号」 2025年1月号より要約)

経営規模=水稲16ヘクタール/ナガイモ、ニンニクなど10ヘクタール
加入のきっかけは職員からのすすめです。
農業の怖いところは、中心になって管理している人に何かあった時に、全て止まってしまうところで、何も無いのが一番良いけれど、「人間なにかしらはあるもの」と思っているので、その時の備えとして加入を決めました。
加入して良かったところは安心できるところ。「なにかあるかも」という不安な部分を収入保険でカバーしてもらっています。
加入を考えている人へ、「自分が倒れたらどうするのか」と考えてみてほしいです。家族のことを思ったら、収入保険は加入した方が良いと思います。
「あらゆる災害に備える」
【岩手県奥州市 佐藤 英雄さん】
(NOSAI岩手 広報紙「結いの大地 NOSAIいわて No.57号」 2024年11月号より要約)

経営規模=リンゴ15.2ヘクタール
収入保険の魅力は「つなぎ資金」があることですね。
昨年は、春先の低温で中心花などに凍霜害を受けて、4月時点で減収が確実になってしまいました。また、降雹や台風7号などの被害もあって、平年の収入の4割ほど減収となりました。
つなぎ資金の受取対象となったことと、農業経費の各種支払いが難しい状況だったので、つなぎ資金を申請しました。保険金の一部を早期に受け取ることができ、農業資材の購入費用などに充てて、無事に支払いすることができました。
あらゆる災害に備えるために、収入保険に加入した方がいいと思います。
「安心した経営づくりのために」
【岩手県紫波町 佐々木 武さん】
(NOSAI岩手 広報紙「結いの大地 NOSAIいわて No.57号」 2024年11月号より要約)

経営規模=ブドウ95アール/水稲16アール
収量の減少だけでなく、さまざまな要因による収入減少を補償する収入保険に魅力を感じ、令和元年に加入しました。補償を充実させるため、保険方式と積立方式を組み合わせて加入しています。
昨年は、春先の降霜や、収穫時期間近の熊や鹿による被害で販売収入が減少しました。被害申請をして保険金を受け取ることができ、加入していて本当によかったと思います。
収入保険は、万が一の時に農家の助けになる保険だと思います。安心して経営を続けていくためにも、加入を迷っている方にはお勧めしたいですね。
「補償のありがたみ実感」
【宮城県蔵王町 佐藤 康宏さん】
(NOSAI宮城 広報紙「和み」No.54 2024年秋号より要約)

経営規模=ナシ2ヘクタール/リンゴ約1.2ヘクタール/ブルーベリー10アール
収入保険は、自然災害によって、ナシやリンゴが変形し収入が減少した際に、農業収入全体を補償してくれると知り、加入を決めました。令和3年や令和4年4月上旬の降霜で、ナシの花芽が凍霜害を受け、変形果等となりました。また、令和5年は猛暑の影響で、肥大期のリンゴの品質が低下し、収量が大幅に減少しました。被害を受け、収入に不安を抱えていましたが、収入保険に加入していたおかげで補償され、安心しました。
霜や猛暑などの自然災害を経験し、改めて収入保険の必要性を実感しました。また、青色申告を長年していたことで、収入保険にスムーズに加入できたので、青色申告をしていて良かったと感じています。
「つなぎ資金、営農継続の一助に」
【宮城県登米市 高橋 勇さん】
(NOSAI宮城 農業共済新聞 2024年11月1週号より要約)

経営規模=ネギ4ヘクタール/水稲30アール
これまで大きな被害がなく営農をしてきましたが、安定した経営を続けていくためにも地域の農家仲間から収入保険を勧められたことが決め手となり、加入しました。その後、加入してすぐ今までに経験したことがない水害や高温といった異常気象による被害に遭い、2年連続で減収となりましたが、保険が適用となり大変助けられました。
また、保険金が支払いされるまでに、無利子で利用できるつなぎ資金を借りられたのも、当面の支払いをするのにとても助かりました。
収入保険は、自分の補償されている金額が明確に分かるので、安心して農業に取り組むことができ、規模拡大や新しい取り組みにも積極的にチャレンジができ、とても助かっています。
「つなぎ融資を人件費や資材費に充当」
【秋田県能代市 合同会社 久保井ファーム 代表社員 久保井 優司さん】
(農業共済新聞 「秋田版」2024年6月1週号より要約)

経営規模=ネギ5.3ヘクタール/キャベツ2.5ヘクタール
2023年7月15日の大雨を含む4日連続の降雨でネギの圃場が1週間滞水し、広範囲で根腐れが生じました。一方、キャベツは7月下旬の定植後、干害に見舞われ、散水や追肥を施すも小玉のまま生育が停止。平年収穫量よりネギが4割、キャベツが8割以上減少したため、11月下旬につなぎ融資を申請し、12月中旬に融資を受けました。
これほどの被害は経験したことがありません。資金繰りに苦しむ中、受け取った融資を人件費や資材費に充当でき本当に救われました。
今後は、ウドやアスパラガスなど冬季のハウス栽培や、カット野菜の製造・販売を検討しています。収入保険の支えがあるので挑戦することができ、心強いです。
「多品目経営にピッタリ」
【山形県舟形町 叶内 富恵さん】
(農業共済新聞 「山形版」 2024年8月2週号より要約)

経営規模=水稲190アール/山ブドウ35アール/タケノコ30アール/アスパラガス17アール
当初は、保険料等の負担を懸念していましたが、試算をしたところ、これまで加入していた水稲共済の掛金と大差なく「今までと同程度の負担で多品目の補償をしてもらえるなら」と、収入保険への加入を決めました。
加入初年度となる2021年は、コロナ禍による米価下落や、低温によるタケノコの収穫量の減少などにより保険金を受け取りました。
クマや鳥による食害や夏期間の高温による農作物被害が心配ですが、収入保険に加入していると安心して営農を続けられます。今後は息子に経営を引き継ぐことを視野に入れつつ頑張っていきたいです。
「“収入保険”が営農する上で心の支えとなっています」
【福島県相馬市 作田 安之さん】
(NOSAI福島 広報紙「NOSAIひかりNo.41号」 2024年9月号より要約)

経営規模=水稲380アール/野菜70アール
NOSAI職員に勧められ、令和元年から収入保険に加入しています。自分の収入をもとに基準収入金額が設定されるという点に魅力を感じて加入を決めました。
令和5年は、夏に異常なほどの高温が続いた影響で米の等級が下がり、野菜も大きな被害を受け減収となりました。収入保険に加入していたおかげで保険金を受け取り、減収分を補てんすることができました。
収入保険への加入は、いざという時の安心感につながり、日々の営農をする上で心の支えとなっています。これからも、皆さんにおいしいと言ってもらえる作物を作ることができるよう、農業を続けていきたいです。
「安心して仕事をするためにも加入を継続したい」
【福島県楢葉町 大谷水稲受託組合 組合長 猪狩 信康さん】
(NOSAI福島 広報紙「NOSAIひかりNo.42号」 2025年1月号より要約)

経営規模=水稲2,600アール
収入保険には令和3年から加入しています。令和5年8月から9月にかけて猛暑が続いた影響で高温障害が発生、品質が低下し収量も減少し収入金額が落ち込んでしまいました。保険金を受け取ったことで、農業機械の整備に充てることができました。
近年、異常気象により米の収穫量が減少したことで、米価が不安定な状態となっています。各地で盗難が多発していますが、盗難に遭った場合も補償対象になると聞いています。安心して農業を続けるために、これからも継続して加入していきたいと思います。
「干ばつの影響で収入減少」
【北海道滝川市 江﨑 正典さん】
(NOSAI北海道広報誌(NOSAIほっかいどう)2023年3月号より要約)

経営規模=小麦、黒大豆、てん菜、ナタネ、エゴマ、ヒエ 約50ヘクタール
農業共済の品目にない作物のウエイトが大きく、特にナタネは収穫時期の降雨が収穫量に甚大な影響を及ぼします。従来の農業共済よりもトータルの販売収入に対して補償される収入保険の方が合っていると感じ、切り替えることに決めました。
令和3年は干ばつの影響で、雑穀類を中心に大きく収入減少が見込まれたため、つなぎ融資の貸し付けを希望しました。
手続きも簡単で、希望してから受け取りまでわずか1カ月程度だったので、年末の経費支払いに充てることができ、とても助かりました。
「加入していなければ営農継続できていなかったかもしれない」
【北海道幌加内町 (株)北村そば農場 代表取締役 北村 忠一さん】
(NOSAI北海道広報誌(NOSAIほっかいどう)2023年1月号より要約)

経営規模=ソバ、大豆138ヘクタール
以前から畑作物共済に加入し、自然災害に備えていましたが、価格低下などのリスクに不安を抱えていたことなどから加入を決めました。
新型コロナウイルス感染症の流行による、外食産業の低迷に伴うソバの価格下落や、翌年の干ばつで収量が大きく減少したことなどから、今まで経験のないほど収入が大きく減少しましたが、収入保険の補償を受け、とても助かりました。
加入していなければ、営農を継続できなかったかもしれません。
「大雨による樹幹浸水や病害などで大打撃」
【青森県弘前市 赤石 正紀さん】
(NOSAI青森広報誌(NOSAI青森)2023年3月号より要約)

経営規模=りんご2.3ヘクタール
令和4年は大雨による樹幹浸水や病害などで大打撃を受けたため、つなぎ融資を利用しました。手続きが煩雑なのではないかと不安に思う部分もありましたが、手続き自体は簡単なもので、無事経営資金に充てることができました。
過去にひょう害で大きく被害を受けたため、その備えとして加入しましたが、今回のようなことがあって収入保険を選択しておいてよかったと思います。異常気象が見られる昨今において、収入保険は経営する上で心強い味方になると感じました。
「病気の治療が長引き収入が大きく減少」
【秋田県大仙市 渡部 良太郎さん】
(NOSAI秋田広報誌(NOSAI)2023年3月号より要約)

経営規模=水稲16.2ヘクタール/ソバ3.7ヘクタール/ダリア3アール
稲作を中心に、プール育苗やドローン防除の導入など、省力化・効率化に取り組んできました。少人数でも作付面積を広げられるように努力してきた一方で、個人の事情による労働力の低下が減収に直結する不安があり、収入保険に加入しました。
一昨年病気を患い、農繁期に手術を行うことになりました。事前にできる限りの準備を進めていたものの、治療が長期に及んだことで予定面積を作付けすることができず、収入が大きく減少しました。
作業労賃や農機具のローン返済などの支払いが続くため、つなぎ融資を申請しました。迅速な支払いのおかげで、本当に助かりました。
「水稲圃場が土砂で埋没」
【秋田県北秋田市 小笠原 昌さん】
(NOSAI秋田広報誌(NOSAI)2023年3月号より要約)

経営規模=水稲13ヘクタール/ヤマノイモ57アール/インゲン2アール
収入保険発足時の平成31年から加入しています。昨年は8月の豪雨で水稲圃場に土砂が流入したほか、野菜も大きな被害を受けました。過去に無いほどの甚大な被害で、収入が大幅に減少しました。
そんな時につなぎ融資を知り、早速手続きをしました。職員に迅速な対応をしてもらい、大変助かりました。無利子で融資を受けられるのは、収入保険の大きな強みだと思います。
さまざまなリスクに対応している収入保険は、魅力的で心強い保険です。万が一に備えることで、安心して農作業に励むことができます。
「病気で計画通りに営農できず」
【福島県田村市 小林 丈一さん】
(NOSAI福島広報誌(ひかり)2023年1月号より要約)

経営規模=水稲4.7ヘクタール/ソバ40アール/タラの芽15アール
近年は過去に類をみない大規模な自然災害が頻発しており、社会的・経済的に大きな被害を与える新型コロナウイルスの流行などにより、経営に不安を覚え、令和3年度から加入しました。
昨年、病気で入院して計画通りに営農できませんでしたが、収入保険のおかげで減収分を補填することができました。支払いも早く本当に助かりました。安定した収入を確保するために、これからも健康を第一に経営努力を重ねていきたいです。
「収入保険は頼れる後ろ盾」
【北海道北見市 (株)豊田ライズファーム 代表取締役 村上 健太郎さん】
(NOSAI北海道広報誌(NOSAIほっかいどう)2023年3月号より要約)

経営規模=水稲(もち米)約35ヘクタール
令和3年にトラクター利用組合の水田を引き継いで(株)豊田ライズファームを設立し、もち米の栽培に取り組んでいます。利用組合の過去実績を引き継いで加入することができることから、令和3年12月から加入しました。
何も起こらないに越したことはないですが、安定した会社経営の観点からも収入保険は頼れる大きな後ろ盾です。収入保険のバックアップがあるので、これから多くのことにチャレンジしていきたいです。
「強風により落果被害」
【北海道増毛町 仙北 要さん】
(NOSAI北海道広報紙(NOSAIほっかいどう)2023年1月号より要約)

経営規模=リンゴ、オウトウ、洋ナシ、和ナシ、モモ、プルーンなど約3ヘクタール
凍霜害や台風による自然災害に加え、取引先の倒産、けがや病気による収入減少などのリスクから農業経営を総合的に守ってくれることに魅力を感じました。また、増毛町では令和4年から農業保険の保険料が2割補助されることになり、収入保険加入1年目の積立金が大きいため、一部でも保険料を負担してくれるのは大変助かりました。
令和4年は8月下旬と9月上旬の強風でリンゴでは品種によって1割、ナシは4割程度の落果被害が発生しました。またコロナ禍により、収穫体験で訪れる団体客の少ない年が続いており、収入保険に加入したことで経営に安心感が増しました。
「基準がはっきりしている点が魅力」
【岩手県北上市 平野 久美雄さん】
(NOSAI岩手広報紙「NOSAIいわて」2022年10月号より要約)

経営規模=水稲11.6ヘクタール/麦1.9ヘクタール
収入保険は、青色申告書類を基に収入の減少を判断するので、基準がはっきりしている点が魅力ですね。収量の減少だけでなく、毎年心配していた米価の下落も補償されると聞き、勧められてすぐに加入を決めました。
加入を迷っている方はNOSAI職員に相談してみるといいですよ。青色申告をしている農家が加入の対象なので、白色申告の方は、まず青色申告を始めてみてはいかがでしょうか。
「幅広い補償が加入の決め手」
【宮城県加美町 杉村 昭宏さん】
(NOSAI宮城広報紙「和み」2022年11月号より要約)

経営規模=水稲(主食用)13.6ヘクタール/もち42アール/飼料用11.7ヘクタール、ネギ1ヘクタール
経営を下支えしてくれる収入保険は、生産している農産物すべてが対象と幅広い補償が加入の決め手となり、令和元年から加入しています。
3年前の台風19号でネギ圃場が冠水し、収穫前のネギが水に浸かってしまいました。ポンプを使って一日中排水しましたが、収穫に大きな影響が出てしまい、経営リスクへの備えが重要だと痛感しました。
昨年はコロナ禍の影響で、米・ネギともに価格は低迷し、大きく収入が減少しました。さらに農業資材や肥料の高騰などで経営を圧迫しましたが、収入保険のおかげで安心して農業経営を行えました。
今後は、収入保険で経営リスクに備えつつ、品質の良い米とネギの生産に取り組むとともに、若手農家の人材育成や確保に力を入れていきたいです。
「収入に見合った補償に安心感」
【宮城県登米市 芳賀 秀二さん】
(農業共済新聞(宮城版)2022年10月5日より要約)

経営規模=水稲2ヘクタール/リンゴ2ヘクタール/モモ40アール
農業は自然が相手なので、保険への加入は必須だと昔から感じています。以前は水稲共済と果樹共済に加入しており、何度か自然災害にも遭ってきました。そんななかで収入保険に切り替えた一番の決め手は、自分の収入に見合った補償が受けられるということです。収入保険では、収量メインの果樹共済ではカバーしきれなかった価格の部分の補償が充実していると感じました。
近年は異常気象、新型コロナウイルス、生産コストの上昇と農家を悩ませる問題が山積です。収入保険で備えながら、今後の経営をより揺るぎないものにし、継続していけるように日々の営農に取り組んでいきたいです。
「米価下落への対応も」
【岩手県奥州市 菊池 克則さん】
(農業共済新聞(岩手版)2022年9月7日より要約)

経営規模=水稲6ヘクタール
「平成5年冷害」を除いて、幸いにも収量が大きく減少することはありませんでしたが、米の価格下落が心配だったので、2020年に収入保険に加入しました。毎年、継続加入の手続きの際に収入額をしっかり把握できるので、翌年の作付計画を立てるときに役立つのもいいところですね。
昨年は米の価格下落で収入が2割減少したので、保険金を受け取れて安心したのを覚えています。
自然災害や価格の変動などは、個人ではどうすることもできません。収入保険はさまざまなリスクから経営を守ってくれます。営農を続けるためにも、専業農家はもっと収入保険を活用したほうがいいと思います。
「大規模なひょう害。収入が半分に」
【岩手県一関市 小山 武さん】
(農業共済新聞(岩手版)2022年9月7日より要約)

経営規模=リンゴ約9ヘクタール
自然災害に備えるために果樹共済に加入していましたが、収量ではなく収入減少を補てんする収入保険に魅力を感じ、2020年に加入しました。
20年6月に一関市内で大規模なひょう害が発生し、生育途中の果実が損傷しました。収入が例年の半分に落ち込んだので、従業員の人件費や資材費などの支払いが不安でしたが、つなぎ融資を申請して各種の支払いに充てることができ、支障なく営農を続けられたので、収入保険制度があって本当に助かりました。
この経験から、私が住んでいる地域でリンゴを栽培する仲間に積極的に収入保険への加入を勧めています。
「ミツバチ経営の支えになる」
【岩手県軽米町 小森 満さん】
(農業共済新聞(岩手版)2022年9月7日より要約)

経営規模=セイヨウミツバチ300群
家族4人、繁忙期は6人を雇用してセイヨウミツバチを飼育し、蜂蜜の収穫のほか、果樹農家にミツバチを貸し出しています。ミツバチや蜂蜜を対象とした保険はこれまでになく、収入減少を幅広く補償する収入保険制度は、安定した経営のために必要不可欠だと思い、20年に加入しました。
昨年は蜜源植物のアカシアが凍霜害の影響であまり開花せず、蜂蜜が十分に集まりませんでした。例年の半分まで出荷量が落ち込み、収入が減少したので、保険金を受け取ることができました。収入保険が経営の支えとなるので安心して作業に取り組むことができ、気持ちに余裕が生まれました。
「つなぎ融資で危機を乗り越えることができた」
【宮城県栗原市 鈴木 善典さん】
(NOSAI宮城広報紙「和み」2022年9月号より要約)

経営規模=キュウリ31アール/ちぢみホウレンソウ20アール
過去に新しい栽培方法に挑戦した際、土壌病害を引き起こしてしまい、収入が大幅に減少してしまった経験があります。
収入保険はこうした挑戦での失敗もカバーしてくれるのと、近年のコロナ禍における収入の不安定さから加入を決断しました。
春からの市場価格下落に加え、自身が新型コロナウイルスに感染してしまい、収穫を断念さざるを得ませんでした。そのため資金繰りが困難になり、苦しい経営状態でしたが、収入保険で無利子のつなぎ融資を受けることができ、危機を乗り越えることができました。
「収入減少の不安を解消」
【宮城県大崎市 渡邊 正彦さん】
(NOSAI宮城広報紙「和み」2022年9月号より要約)

経営規模=水稲7.5ヘクタール/大豆6.5ヘクタール/ナス7アール
令和元年の台風19号によるハウスの浸水被害で収入減少を経験し、補償の必要性を感じていました。また、昨今の自然災害の増加や、農産物価格の下落などを考えると、収量より農業経営全体の収入をカバーする収入保険に大きな魅力を感じ加入しました。
加入後は、令和3年の米価の下落などに対応してもらい、安心して農業を続けることができました。
今後長男が就農予定なので、収入保険を頼りに、法人化を目指したいと考えています。
「充実した補償の範囲に魅力」
【宮城県亘理町 遠藤 正志さん】
(NOSAI宮城広報紙「和み」2022年9月号より要約)

経営規模=キク1ヘクタール/水稲6ヘクタール
収入保険に加入して3年目になります。これまでナラシ対策に入っていたのですが、充実した補償の範囲に魅力を感じ加入しました。
経営する上で、キクの価格が安定しないことが悩みでしたが、昨年は新型コロナウイルスの影響で葬儀にキクの花を使うことが激減しました。
園芸施設を維持する費用も大きいため、今回収入保険で補償してもらえたことで大変助かりました。安定した営農を続けるためには必要な保険だと思います。
「被害をうけた経験から」
【秋田県横手市 丹 貴史さん】
(NOSAI秋田広報紙「NOSAI」2022年9月号より要約)

経営規模=小ギク61アール/輪ギク34アール(ともに露地)
昨年6月、局地的な降ひょう被害を受け、盆用の輪ギクが全滅。その後、彼岸用の管理に努めましたが、出荷量は前年より4万本減少してしまいました。キクは価格を補償する制度もありますが、出荷できない場合は補償の対象になりません。それまで大きな被害を受けた経験がなく、保険の必要性を感じていませんでした。昨年の被害を受け、保険による備えが大切だと思い、収入保険の加入を決めました。
今年も天候に悩まされましたが、収入保険が心の支えになり、加入前よりも安心して営農できています。
「恐れずに挑戦できる」
【秋田県大仙市 農事組合法人はちまんの里 代表 鈴木 正雄さん】
(NOSAI秋田広報紙「NOSAI」2022年9月号より要約)

経営規模=水稲45ヘクタール/大豆29ヘクタール/野菜90アール/ブドウ50アール
平成29年7月に近くの川が氾濫し、水稲と大豆に大きな被害を受けました。当時は水稲・大豆共済で補償されましたが、近年は農業共済事業で補償されない品目の栽培が増えています。再び水害が起きることを考えると不安ですが、収入保険では栽培品目が全て補償されますし、それぞれの保険に加入するより掛金が安くなるため、収入保険を選択しました。
最近は出荷直前の果物が盗難に遭ったニュースを聞きますが、この場合も補償されますので、安心してブドウを栽培できます。また、土壌が合わず、ニンニク栽培に失敗した経験があります。新たな作物の栽培はリスクがありますが、収入保険のおかげで恐れずに挑戦できると思います。
「大雨により河川が氾濫 作物が冠水」
【青森県東北町 鶴ケ崎 勝也さん】
(NOSAI青森広報誌「NOSAI青森」2022年7月号より要約)

経営規模=水稲79ヘクタール/たまねぎ2.3ヘクタール
2021年8月の温帯低気圧による大雨により、河川の氾濫で作物が冠水し大きな収入減少が見込まれたためつなぎ融資を申請しました。つなぎ資金のおかげで会社経営資金に充てることができ、とても安心しました。
価格低下を補償する収入保険は会社経営をするにあたって掛金を含めてとても魅力を感じ加入しました。
今後は野菜の規模拡大に取り組みたいと考えています。また、地域の方々と連携を深め、自分が先頭に立って次世代の農業につなげていきたいと思います。
「個人の収入に基づく収入保険は頼りになる」
【秋田県大仙市 太田 淳さん】
(NOSAI秋田広報紙「NOSAI」2021年11月号より要約)

経営規模=水稲4.1ヘクタール
以前は水稲共済の一筆方式とナラシ対策で備えていましたが、収入保険に魅力を感じ、一筆方式が廃止になるタイミングで移行しました。
加入初年となった2021年は、刈取時期の長雨による水稲が倒伏と価格低下により収入減少となり、保険金を受け取りました。
ナラシ対策は、地域平均で価格低下や減収となった場合に補てんされるため、個人の収入に基づく収入保険は頼りになります。天候は自分の力ではどうにもできませんし、けがで収入が減少する可能性もあります。
魅力が多い収入保険に今後も期待しています。
「2年連続で霜の被害が」
【福島県須賀川市 渡辺果樹園 渡辺 喜則さん、佳子さん】
(NOSAI福島広報紙「ひかり」2022年7月号より要約)

経営規模=モモ100アール/和ナシ300アール/洋ナシ70アール
収入保険は経営の安定のために、初年度から加入しています。
10年に1度のレベルと言われるような大きな災害が頻発するようになりました。対策はしていましたが防ぎきれず、一昨年と昨年は霜の被害により着果量が減少し、保険金を受け取りました。
保険金の支払いは早く助かりました。おかげで農作業が滞りなくできるようになり、不安がなくなりました。
「収量をあげる経営努力を」
【福島県田村市 石井 定光さん】
(NOSAI福島広報誌「ひかり」2021年11月号より要約)

経営規模=水稲74アール/ミニトマト20アール
JAを通じて、出荷をしていますが、野菜を補償する保険はなく、経営に不安を抱えていました。そんな中、収穫量減少だけでなく、病気やケガ・価格の低下などさまざまな要因での収入減少を補償できるとのことだったので、加入を決めました。
品種転換をしたところ、思うように収量が採れず収入が大きく減少してしまいました。しかし、収入保険が大きく補てんしてくれたことで、次期作の苗代に回すことができ、本当に助かりました。
これからも収量をあげる経営努力をしていきたいです。
「米価の下落やイノシシによる被害」
【福島県塙町 下重 繁男さん】
(NOSAI福島広報紙「ひかり」2022年4月号より要約)

経営規模=水稲20ヘクタール
以前から青色申告をしており、自然災害や米価の下落だけではなく、けがや病気で収穫ができない場合なども補償がされるという点で魅力を感じ、加入を決めました。
2020年は新型コロナウイルスの影響による米価の下落や、イノシシによる被害で収入が大きく減少しましたが、保険金のおかげで翌年の農業経営が非常に助かりました。
2021年も米価の下落により収入が大きく落ち込みました。不安定な情勢の中で安定した収入を維持するためにも、収入保険への加入は必要だと感じています。
収量減少と価格低下による収入減少を補償 「収入保険で農業経営が救われました」
【岩手県普代村 中居 昭彦さん】
(農業共済新聞(岩手版)2021年9月2週号より要約)

経営規模=原木シイタケ2万1千本
2020年は春先の低温や少雨の影響で、露地栽培のシイタケが霜と乾燥の被害を受け、収量は前年の3分の1程度に。さらにコロナの影響で飲食店からの需要が減少し価格も下落したため、収入が前年の半分にまで落ち込みましたが、収入保険に加入していたので、保険金を受け取ることができ、農業経営が救われました。
収入保険の加入条件は青色申告を行っていることなので、仲間のシイタケ農家にはまず青色申告を始めることを勧めています。
「ハウス全てで被害 補償の厚さに助けられました」
【秋田県小坂町 目時 勝則さん】
(NOSAI秋田広報誌「NOSAI」2022年7月号より要約)

経営規模=水稲34アール/トマト30アール/アスパラガス75アール/花き20アール/その他野菜10アール
昨年、高温や病害による作物の生育不良で収入が減少しました。特にトマトの「かいよう病」被害の影響は大きく、ハウス3棟全てで被害を受け、当時は廃業を考えるほどでした。
そんなとき、つなぎ融資を思いだしすぐに申請。融資を受けるまでが迅速で、営農を継続することができました。税務申告後に支払われた保険金は、春の運転資金に充てることができ、補償の厚さに助けられました。
また、最高値で取引される時期に単価が下落したことも収入に影響しました。農家の努力だけではどうにもできない市場価格の下落にも対応している収入保険は、今後も農家の助けになると思います。
「青色申告にもメリット」
【宮城県美里町 仁木 弘恵さん、正宏さん】
(農業共済新聞2022年7月6日より要約)

経営規模=主食用米20ヘクタール/飼料用米8.5ヘクタール/小麦8ヘクタール/大豆3ヘクタール
最近は個人経営で使える補助金の選択肢が少ないですが、収入保険に加入しているおかげで、農機の支払い計画が立てやすいです。
加入要件である青色申告は、実家を継いで経営開始した当初からパソコンソフトを使い、仕訳などは地域の青色申告会で教わりました。専従者給与を控除できる点なども利点です。
2021年産は米価下落や天候不良による転作作物の減収により保険金等を受け取り、収入保険の補償が支えとなりました。
「病気やけがによる収入減少も補償 年内につなぎ融資を受け助かりました」
【北海道士別市 遠藤 英俊さん】
(農業共済新聞2021年12月1週号(北海道版)より抜すい)

経営規模=秋まき小麦10ヘクタール/春まき小麦6ヘクタール/大豆20ヘクタール/澱粉バレイショ2ヘクタール/テンサイ9ヘクタール
自然災害だけ補償する農業共済より、病気やけがによる収入減少が補償される収入保険に切り替えた方が安心して営農ができるのではないでしょうか。さらに、積立金を除いた保険料が(農業共済と比べて)安く抑えられると思ったことから、収入保険に加入しました。
加入した年に、バレイショの被害が大きく、収入減少が見込まれたため、つなぎ融資を申請しました。農業共済の共済金支払いは、作物によっては時期が遅れるため、年内につなぎ融資を受けることができて助かりました。
「米価が下落 つなぎの運転資金として」
【秋田県大仙市 SATORUファーム 代表 伊藤 悟さん】
(農業共済新聞2022年6月22日(秋田版)より抜すい)

経営規模=水稲49ヘクタール/大豆2ヘクタール/ダイコン3ヘクタール/イチゴ12.5アール
昨年、米価が下落し収入が減少しました。申請から1ヶ月ほどでつなぎ融資を受け取り、資材代などの支払いに充当することができました。
水田活用の直接支払交付金などは年末以降に支払われるため、収入が減少した場合はつなぎの運転資金が必要。つなぎ融資は以前から魅力的だと思っていましたが、実際に受けられて助かりました。
元々は、水稲共済と大豆共済に加入していましたが、法人化するタイミングで収入保険に移行しました。法人化で経営規模が拡大し、収入も増えていくなか、収入保険は収入の減少が1割を超えた際に補てんが受けられるので、加入すれば安心して営農ができると考えました。農業法人は従業員の生活に対して責任があるため、加入に迷いはありませんでした。
「モモのせん孔細菌病 つなぎ融資はわかりやすい制度」
【福島県桑折町上郡 大槻 栄之さん、典子さん】
(NOSAI福島ホームページより抜すい)

経営規模=水稲60アール/モモ150アール/リンゴ40アール
家族で果樹と水稲を経営しています。収入保険に加入した一番の決め手は、補償が幅広いことです。果樹や水稲共済では、品質低下だけだと補償の対象になりませんが、収入保険は減収のほか、品質低下や市場価格の下落などすべての収入減少に対応するので、安心して営農できます。
一昨年、モモのせん孔細菌病によって収入が減少し、つなぎ資金を申し込みました。初めてで不安でしたが、実際に下がった額を申告すればよいので、わかりやすい制度だと思います。申告してから約3週間で支払いがあり、大変助かりました。無利子なのもいいですね。昨年は、一昨年以上に深刻なせん孔細菌病の被害を受けましたが、収入保険に加入しているので心強いです。
「ナシの降霜・降ひょう被害 つなぎ融資で助かりました」
【秋田県男鹿市 鈴木 慶美さん(63)】
(NOSAI秋田広報誌NOSAI2022年3月号より抜すい)

経営規模=ナシ1.2ヘクタール
昨年は降霜や降ひょう被害で、ナシの収量が平年の5割近くまで減りました。毎年のように被害を受けていますが、過去2年は全国的に収量が減っていたことから市場価格が上がり、収入減少が緩和されていました。
昨年は例年以上に被害が多いため収入減少に歯止めがかからず、困っていたところ、収入保険のつなぎ融資を知っていたため、すぐ組合に連絡しました。
迅速な対応のおかげで年内につなぎ資金が振り込まれ、大変助かりました。
「大雪でハウス倒壊 露地作物の降ひょう被害」
【秋田県横手市 柴田 敏一さん(73)】
(NOSAI秋田広報誌NOSAI2022年3月号より抜すい)
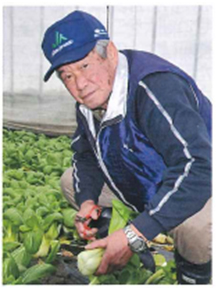
経営規模=水稲6ヘクタール/キク(露地)1ヘクタール/ハウス4棟(キク・チンゲンサイ)/ソバ1ヘクタール
冬に栽培するチンゲンサイが、大雪によるハウス倒壊の影響を受けました。また、露地のソバやキクが6月の降ひょう被害を受け、収量が減少。特にキクは盆に出荷する分がほぼ収穫できませんでした。
全体の収入が平均収入から約4割減る見込みで、10月初めにつなぎ融資を受けました。資材の支払いや農機具のローン返済などに間に合ったのでよかったです。
その後、米の概算金が発表され、予想を上回る下落となりました。融資をうけていてよかったと改めて感じました。
「市場価格の低下、減収などさまざまなリスクに対応できる」
【北海道池田町 (株)十勝美濃農場 代表 美濃 志拓さん(36)】
(農業共済新聞2021年11月1週号より抜すい)

経営規模=タマネギ、キャベツ、アスパラガスなど56ヘクタール
畑作物共済に加入していましたが、市場価格に大きく左右される野菜の作付けが中心だったため、不安を抱いていました。価格の低下や取引先の倒産などを補てんできる収入保険を知り、2019年から加入しています。
2020年は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い緊急事態宣言が発令され、野菜の市場価格が低下しました。さらに干ばつの影響も重なり、作付面積が多いタマネギが大幅な減収となりました。さまざまなリスクに対応できる収入保険のありがたみを実感できました。
今後は自分でも簡単に加入申請ができる共通申請サービスにもチャレンジしたいです。
「米価下落で打撃もつなぎ融資を活用。経営継続の一助に」
【宮城県栗原市 (株)石川アグリ 代表 石川 和彦さん(60)】
(農業共済新聞2022年2月2日より抜すい)

経営規模=水稲32ヘクタール
米の概算金が60キロ当たり9,100円と知ったときはショックでした。下落は予想していましたが、まさか1万円を下回るとは。
収穫量を上げて補おうとしましたが、予想を超える下落でカバーできませんでした。
機械のローンが払えないと心配だったため、12月つなぎ融資を申請し受け取りました。
シンプルに基準収入の9割に満たなかったら、補償してもらえる仕組みは安心です。21年産の概算金低下を考えれば加入していてよかったです。
「米価下落で予想外の打撃 つなぎ融資が経営継続の一助に」
【秋田県由利本荘市 伊藤 孝弘さん(46)】
(農業共済新聞2022年2月9日(秋田版)より抜すい)

経営規模=水稲8ヘクタール
2021年産の米価は、外食産業が冷え込み、米の需要が減少していたので、買い取り額が低下すると予想していましたが、想像より下がり幅が大きかったです。
収穫後に支払う資材費について、資金が一時的にショートしてしまう可能性があったため、つなぎ融資を申請。資材費の支払いなどに充てることができました。
収入保険への加入を検討した時は、自分が体調を崩し営農ができなくなることや、民間の米卸業者が倒産してしまった場合などを想定していました。今回のような価格低下にも対応できる収入保険は心強い存在でした。
「11年間で初めての被害 つなぎ融資で雇用が継続できた。」
【岩手県八幡平市 宮野 亜由美さん(39)】
(農業共済新聞2022年3月2日より抜すい)

経営規模=リンドウ1.3ヘクタール
報告・連絡・相談の徹底による作業の効率化などの工夫で、子育て中の女性8人をパート従業員として雇っています。
4月下旬から5月下旬にかけての低温で株が弱体化したほか、収穫前の8月に高温障害や褐斑病、ダニが発生し、収入が平年より約6割落ち込みました。11年間農業をしてきて初めてでした。
11月につなぎ融資を受け取り、経営を継続。12月に機械のローン支払いがあるので、つなぎ融資がなければ厳しかったです。22年度の予算を安心して考えられ、雇用も継続できました。
「価格下落や高温などによる収入減の支えに」
【秋田県由利本荘市 農事組合法人 平根ファーム 理事 黒木 重徳さん(69)】
(NOSAI秋田広報紙「NOSAI」2022年1月号より抜すい)

経営規模=水稲43ヘクタール/ソバ7ヘクタール/アスパラ4ヘクタール、リンドウ3ヘクタール/キャベツ2ヘクタール、小ギク1ヘクタールほか野菜など 計68ヘクタール
全品目をカバーできることや、価格下落など、水稲共済やナラシ対策では対象外の事例も補償されることから、加入を決めました。
令和3年は水稲の価格下落が経営に大きく影響しました。また、夏の高温がリンドウの生育を一気に早め、開花が特定の時期に集中し、収穫が追い付かず出荷本数が落ち込むなど、前年同様の売上は厳しい見込みです。
そんな中、つなぎ融資の存在を知り、すぐにNOSAIに連絡したところ、1カ月以内に融資を受けることができました。調達した資材や作業員への給与の支払いなどに遅れが出ず、信頼関係を保つことができて安堵しています。
「青色申告に基づいた農業収入全体に対する補償に魅力」
【岩手県北上市 菊池 顕裕さん(61)】
(NOSAI岩手広報紙「結いの大地NOSAIいわて」2021年8月号より抜すい)

経営規模=水稲24ヘクタール
今までは水稲共済に加入していましたが、青色申告の正確な数字で収入減少を判断し、農業収入全体を補償してくれることに魅力を感じ、令和2年に収入保険に移行しました。
加入時に必要な書類の準備は大変でしたが、NOSAI職員がサポートしてくれたので、スムーズに手続きを終えることができました。
米の価格低下などが心配なので、今後も加入を続けたいと思います。
「凍霜害など予期しない災害による収入減の支えに」
【山形県天童市 関 政孝さん(38歳)】
(農業共済新聞2021年11月3週号より抜すい)

経営規模=オウトウ約80アール/リンゴ20アール/西洋ナシ60アール
今年の4~5月に発生した凍霜害でオウトウや西洋ナシの収量が大きく減少し、収入減少が見込まれたので、つなぎ融資を申請し8月に受け取りました。営農継続できたことに安堵しています。
収入保険に加入する前は、凍霜害は補償されない果樹共済の特定危険方式「減収暴風雨方式」に加入していました。最近は各地で予期しない被害が起きていて、経営全体を補償してくれる収入保険に移行しました。
今回の被害を考えれば、収入保険に移行していて本当に良かったです。
「幅広い品目が対象で、トータルで経営を補償してもらえる点に魅力」
【山形県白鷹町 横山 聡さん(38)】
(農業共済新聞[山形県版]2021年3月1週号より抜すい)

経営規模=水稲10ヘクタール/エダマメ4ヘクタール/ハウスダリア・啓翁桜・トウモロコシ・加工用/キャベツ9ヘクタール
多品目を栽培することで、災害や価格変動のリスクを回避しているため、収入保険への加入を迷っていましたが、新型コロナウイルスの影響から、より経営リスクを抑えたいと考え、21年産から収入保険に加入しました。これまで補償のなかった品目が対象になり、トータルで経営を補償してもらえる点が魅力です。
これまでもリスク回避に努めてきたことから、現在の経営状況に合わせ、1年目は保険方式の補償の下限を70%で加入しました。2年目以降は掛金の変動を見ながら、毎年この割合を見直していくつもりです。
「米価下落の影響による収入減の支えに」
【青森県中泊町中里 松坂 龍美さん(59歳)】
(NOSAI青森職員によるインタビューより)

経営規模=水稲10ヘクタール/トマト10アール
収入保険は制度開始初年度から加入しています。
これまで収入が大きく減少したことはありませんでしたが、令和3年は、昨年に比べて米価が大きく下落したことにより、収入減となる見込みです。
12月には農機具や資材などの支払いが多くあるため、資金繰りが不安でした。そこで以前、NOSAI職員から聞いていたつなぎ融資を申請したところ、申請から約1か月程度で受け取ることができ、とても助かりました。収入保険に加入していて本当に良かったと、今では安心しております。
「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う比内地鶏の取引減少による収入減の支えに」
【秋田県大館市 株式会社彩景農場 代表取締役 虻川憲一さん(47歳)】
(農業共済新聞[秋田県版]2021年6月2週号より抜すい)

経営規模=主食用米7.9ヘクタール/飼料用米7.6ヘクタール/比内地鶏1万羽/採卵鶏1万2千羽
以前は水稲共済と収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)に加入していましたが、比内地鶏の補償が無かったため、収入保険に移行しました。
比内地鶏は年間1万羽を出荷する予定で毎月約850羽を導入していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、出荷先との取引が大きく減少し、出荷ができずに収入が大きく落ち込みました。
経費の支払いができるか不安でしたが、つなぎ融資を申請したところ、手続きから1カ月もかからず支払われ、早くて驚きました。収入保険が無かったらと思うと怖い気持ちがあり、加入していて本当に良かったです。
「りんごの価格低下などさまざまな減収を補償してくれることに魅力」
【青森県板柳町 永田 洋亮さん(42)】
(NOSAI青森広報紙「NOSAI AOMORI」2021年1月号より)

経営規模=リンゴ258アール
近年は、台風等の自然災害による被害が多く発生しており、安定した経営が難しくなっています。
収入保険は、自然災害による減収だけではなく、価格の低下や風害や凍霜害等による品質の低下も補償の対象となります。今まで果樹共済では対応できなかった部分も補償されるため、安心して農作業に集中することができ、品質の良いりんごをお客様に出荷できる点も大変助かります。
「さまざまな減収を補償してくれることに魅力」
【北海道北見市 原谷 義成さん(45)】
(農業共済新聞[北海道版]2020年11月1週号より抜すい)

過去に台風の影響で半分以上の作物が被害を受け、経営に大きな打撃を受けましたが、当時は収入減少を補償する保険はありませんでした。
農業収入全体を補償できる保険が無いかと模索していたところ、NOSAIが開催した説明会で収入保険の補償内容を知り、すぐに加入を決めました。
農業共済では、自然災害による補償や対象品目が限られているため、野菜栽培中心の経営をサポートすることができませんでしたが、収入保険は、品目にかかわらずさまざまな減収を補償してくれることが魅力です。
「作物ごとに別々の事務手続きを行う必要がないことに魅力」
【秋田県美郷町 佐藤 久 さん(57歳)】
(NOSAI秋田広報紙「NOSAI」2021年5月号より)

経営規模=大豆20ヘクタール/水稲13ヘクタール
来年産から一筆方式に加入できなくなることや、補償割合の高さを考えて、今年から収入保険に加入しました。
ナラシ・水稲共済・大豆共済の事務手続きを別々にする必要がないのが魅力的です。
体調を崩して営農できなくなった場合も補償対象になるので安心です。
「補償割合とつなぎ融資に魅力」
【秋田県大仙市 伊藤 悟 さん(67歳)】
(NOSAI秋田広報紙「NOSAI」2021年1月号より)

経営規模=水稲43.5ヘクタール/大豆7.3ヘクタール/イチゴ12.5アール
過去に水稲共済金の支払い対象になったことがありますが、一筆方式では平年の収量の3割までの収量減が足切りとなります。
収入保険では収入が基準収入の9割を下回った場合に保険金が支払われるため、令和3年分からの加入を決めました。
収入減少が見込まれる場合は、保険金の前倒しとなるつなぎ融資が受けられることも魅力的です。
「採種や価格低下などが補償されることに魅力」
【北海道由仁町 中嶋 洋美さん(49歳)】
(農業共済新聞[北海道版]2020年9月1週号より抜すい)

経営規模=水稲13ヘクタール/タマネギ・ホウレンソウの採種(ビニールハウス12棟)
農業共済では対象にならない採種や価格低下などが補償の対象になるので、収入保険の方が良いと判断し加入を決めました。
主食用米だけではなく、飼料用米や加工用米の栽培も始めようと思っています。新しいことを始めるときは、収入面など心配もありますが、収入保険はつなぎ融資制度もあり、安心して営農することができます。
保険を使わず営農できるのが一番ですが、いざというときに農家の味方になってくれる保険であって欲しいです。
「干害によるエダマメの被害を補てん」
【秋田県大館市 株式会社ファーム畠山 代表取締役 畠山 博実さん】
(NOSAI秋田広報紙「NOSAI」2020年9月号より抜すい)
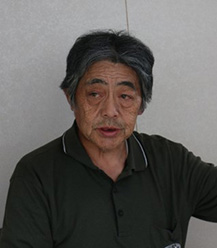
栽培規模=水稲 32ヘクタール/大豆 16ヘクタール/エダマメ 11ヘクタール/ウド 1ヘクタール
昨年は6月に降雨量が極端に少なかったため、干害によりエダマメが大きな被害を受けました。
今回、収入保険の補てん金を受けとりましたが、補てん金の額に満足しています。私どもの場合、年々面積を拡大しているため、それに合わせて収入も大きくなっています。収入保険の場合、単純に過去の平均ではなく、収入の上昇傾向も考慮して補てん金額を設定できるのがいいですね。
今年は新型コロナウイルスや九州豪雨などがあり、農業をやる上での不安が尽きません。そういった中で収入保険は農家になくてはならない保険だと思っています。
「野菜の市場価格の低下による収入減の支えに」
【北海道大樹町 伊藤 幸一さん(39)】
(農業共済新聞[北海道版]2020年4月1週号より抜すい)

経営規模=ブロッコリー10ヘクタール/アレッタ4アール
2019年は野菜の収量は平年並みでしたが、市場価格が下がり、収入の減少が見込まれたので、事故発生の状況をNOSAIに通知し、つなぎ融資を希望しました。
融資の手続きは簡単で、貸し付けを希望してから1カ月程度で資金をスムーズに受けることができました。借入金の返済など、収入が減少した影響を最小限にとどめることができ、とても助かりました。
収入保険に加入し、収入減少への補償を受けられることで経営が安定しました。これからは新しい野菜の栽培を始め、経営の幅を広げるためにさまざまなことに挑戦していきたいです。
「りんどうの品質低下による収入減の支えに」
【秋田県由利本荘市 村上 幸喜 さん(50)】
(NOSAI秋田広報紙「NOSAI」2020年9月号より抜すい)

経営規模=水稲5ヘクタール/りんどう70アール
2019年は雨が少なく水不足になったため、花の色乗りが悪かったり、葉が日焼けしてしまう等、りんどうの品質が低下し、収入が減少してしまいました。
私は水稲とりんどうの複合経営を行っていますが、りんどうの収入は収入全体の3/4ほどを占めるため、被害が発生すると大きな打撃となってしまいます。
収支を概算し、肥料代や農薬代など必要経費の支払いに支障が出ることが分かったので、NOSAI職員に相談し、つなぎ融資の申請をしたところ、すぐに振り込まれたのでとても助かりました。
「野菜の収量減と価格低下で補てん」
【青森県つがる市 鳴海 晋さん(57)】
(NOSAI青森広報紙「NOSAI AOMORI」2020年7月号より)

栽培規模=水稲5.5ヘクタール/長いも80アール/にんにく80アール/ごぼう80アール/にんじん1ヘクタール
令和元年は、高温による発芽不良や病害虫の発生で野菜の収量減となったことに加え、栽培する全ての野菜の市場価格が低下したため、大きな収入減少となりました。
そのため、保険期間中に無利子のつなぎ融資を利用し、農機具や肥料の支払いに充てていました。また、本年5月に、つなぎ融資に追加する形で補てん金を受け取りました。実際に補てん金が支払われるとやはり安心感がありますね。
農業経営は自然災害をはじめ、様々なリスクを抱えています。経営安定には収入保険は不可欠です。
「災害に直面し収入保険の良さを再認識」
【秋田県東成瀬村 佐々木 省吾さん(71)】
(農業共済新聞[秋田県版]2020年5月1週号より抜すい)

栽培規模=菌床シイタケ ハウス3棟(1万4千菌床)
以前、雪害によるハウスの倒壊で、シイタケが大きな被害を受けました。シイタケが不作の際に補償する制度ができれば良いと思っていた時に、収入保険のことを知り、加入を決めました。
2019年1月の大雪でハウス1棟の大部分が倒壊し、例年は3月に行う、シイタケの菌床に種菌を付ける作業ができなくなり、秋にハウスが再建されるまでの間の収入が無い状況になりました。保険金の支払いは翌年と聞いていましたが保険期間中は無利子のつなぎ融資を受けることができました。災害に直面し改めて、収入保険は良い制度だと感じました。
保険金をいただき栽培を続けることができているので、今後法人化を視野に菌床シイタケ生産を続けていく考えです。
「生産者の病気やけがのリスクにも備える」
【岩手県一関市 佐藤 修司さん(56)】
(NOSAI岩手広報紙「結いの大地 NOSAいわて」2019年1月号より)

経営規模=シクラメン、ラベンダー、クローバー ビニールハウス18棟(40アール)
自然災害への補償はもちろんですが、収入保険で特に魅力を感じたのは「生産者の病気やけがが原因で作業ができずに、収入が減少した場合も補償の対象となる」という点ですね。
5年前に入院して、生産現場から離れた時期がありました。残されたスタッフは私の分も頑張ってくれましたが、品質低下は避けられませんでした。やむを得ず花を廃棄することになり、収入が減少してしまいました。
健康第一を心掛けていますが、不安も感じてしまいます。「誰かが働けなくなった時」への備えが必要だと思いました。
収入保険に加入することで、そういった場合のリスクを恐れずに、積極的な商品開発ができると考えています。
「収入を安定させ雇用を確保する」
【岩手県北上市 伊藤 敦さん(57)】
(NOSAI岩手広報紙「結いの大地 NOSAいわて」2019年1月号より)

経営規模=水稲30ヘクタール/リンゴ1.9ヘクタール
農産物の販売収入全体をカバーするということで、収入保険への加入を決めました。
近年は台風の発生が多く、自然災害は自分たちの努力だけでは避けられないことを実感しています。昨年も、収穫期にリンゴの落果などの被害を受けました。強風で木の枝などに擦れて傷がついた果実は、販売価格が安くなったり売り物にならないこともあります。
リンゴ栽培は手間がかかる作業も多いので、パートを雇っています。もし収入がなくなれば、人件費を支払うことができません。パートの方々がいないと、栽培にも影響が出る恐れがあります。
自分の経営を考えると、収入保険に加入することが必要だと思いました。保険は、万が一の事態に備える「お守り」です。
「経営品目全体の補償が魅力的」
【岩手県遠野市 勘六縁 代表 菊池 陽佑さん(35)】
(NOSAI岩手広報紙「結いの大地 NOSAIいわて」2020年1月号より)

栽培面積=「亀の尾」1.5ヘクタール、「遠野4号」3ヘクタール、「ササニシキ」10アールほか
自然栽培で水稲を栽培しています。以前は水稲共済に加入していましたが、自分の栽培方法などを考えて補償の幅が広い収入保険を迷わず選びました。
勘六縁ではインターネット販売のほか、寿司店にも卸しています。今後は、販路拡大のために水稲以外の作物の栽培も考えているので、経営品目全体の販売収入を補償する収入保険は魅力的です。
「営農組合の構成員で加入しました」
【岩手県紫波町 十二神農業生産組合 事務局 細川 高幹さん】
(NOSAI岩手広報紙「結いの大地 NOSAIいわて」2020年1月号より)

営農状況=水稲約34ヘクタールほか
水稲共済よりも補償範囲が広いので、営農組合(構成員17人)として収入保険に移行しました。任意組合なので、加入は構成員個々です。
日時を決めて構成員に集まってもらい、NOSAI職員の方に加入手続きをお願いしました。
全員分の手続きが2時間ほどで完了したので、事務の負担は感じませんでした。タブレットを使って、保険料などがすぐに計算できるのもいいですね。
「興味を持ったら一度相談を」
【青森県中泊町薄市 株式会社秋元 代表 秋元 正和さん(41)】
(NOSAI青森広報紙「NOSAI AOMORI」2019年11月号より抜すい)

栽培規模=水稲21ヘクタール、大豆1ヘクタール
収入保険を知ったきっかけは、NOSAIの地区担当者より「新しい保険がNOSAIで始まるので内容を聞いてみませんか」との声でした。
2人で営農しているため、1人でも怪我をしてしまうと農作業に支障が出てしまうことに不安を感じていました。
収入保険では「加入者本人や一緒に営農している方の怪我による収入減少も補償する」との説明を受け、収入保険に対し興味を持ちました。
その後も、収入保険の仕組みや掛金など、地区担当者の丁寧な説明が後押しとなり、収入保険への加入を決めました。内容を聞いてみたいという方は、地区担当者に一度相談してみてはいかがでしょうか。
「樹体共済とセット加入がオススメ」
【山形県天童市 大山 修一郎さん(66)】
(NOSAI山形広報紙「NOSAIやまがた」2019年9月号より抜すい)

経営規模=ぶどう1.5ヘクタール、おうとう30アール、 ラ・フランス20アール
私の家は代々続くぶどう農家です。デラウェアから始まりオリンピアを栽培していましたが、現在は全てシャインマスカットに切り替えました。収入の柱となるシャインマスカットが裂果して売り物にならなかった苦い経験と、いずれ息子たちへ安心して経営移譲したい思いから加入を決めました。
収入保険のようにトータルでみてもらえる保険は他にはないので期待しています。私の場合、果樹の樹体共済は継続加入しました。重複加入できない類似制度もあるようですが、資産を補償する共済はそのまま加入できるので、収入保険と両方加入するのがお勧めです。
「啓翁桜や枝豆も対象」
【山形県白鷹町 サンファームしらたか 代表理事 樋口 太一さん(62)】
(NOSAI山形広報紙「NOSAIやまがた」2019年9月号より抜すい)

経営規模=水稲61ヘクタール/WCS用稲4ヘクタール/啓翁桜11ヘクタール/枝豆4.3ヘクタール/スイートコーン1ヘクタール/ハウスメロン33アール/ほうれん草13アール/小松菜5アール
共済制度では補償がなかった啓翁桜や枝豆なども対象になる点が魅力でした。掛金等には国庫負担があり、保険方式の掛金率が1%程度にとどまったので、これなら加入できると理事会で決定しました。
法人同士で情報交換ができるように、ぜひほかの法人にも加入してほしいですね。コメ以外の作物も生産しているうちの経営スタイルには、収入保険が合っていると思います。今後、法人の経営を若い世代に交代したとき戸惑うことがないように、税や保険の分野などスムーズに引き継ぎをしていきたいです。
「つなぎ融資で来年の資材費を確保」
【岩手県軽米町 菅原 敏見さん(59)】
(NOSAI岩手の担当職員によるインタビューより)

栽培規模=原木シイタケ(ほだ木6万本)
原木シイタケは露地栽培のため、天候に左右されやすい作物です。これまで原木シイタケを対象とした保険はなく、農業経営に不安がありましたが、NOSAIの広報紙などで収入保険を知り、加入しました。
水管理は徹底していますが、昨冬は積雪が少なく今年の春も雨があまり降らなかったため、ほだ木が乾燥してシイタケの収穫量が減少しました。収入の減収が見込まれたため「つなぎ融資」を申請しました。
つなぎ融資のおかげで、来年の栽培に必要な資材のための資金を確保することができました。手続きは簡単で、無利子で融資を受けられたので良かったです。
農業を営む上で、無保険はとてもリスクが高いと思います。収入保険に加入することで毎年安心して農業経営ができるので、キノコを栽培する仲間にも加入を勧めています。
「市場価格の変動リスクに備えて」
【北海道芽室町 黒田 栄継さん(43)】
(農業共済新聞[北海道版]2019年11月1週号より)

経営規模=小麦7ヘクタール/バレイショ5ヘクタール/ナガイモ3.8ヘクタール/ゴボウ3.8ヘクタール/スイートコーン3ヘクタール/ユリネ2ヘクタール/ワイン用ブドウ0.7ヘクタール
ナガイモなどの野菜の市場価格の変動にリスクを感じています。契約栽培を増やして経営の安定を図っていますが、万全ではないので、価格低下などによる収入減少も補償対象の収入保険に加入しました。
収入保険の保険料は、被害がなければ年々下がっていきます。努力の成果が反映されるので頑張りがいがありますね。
加入申請の際は、過去の青色申告実績を整理することによって、自分の経営を改めて把握する良い機会になりました。
品目ごとの収入の増減が相殺されるのではという考え方もありますが、自分の経営に必要な保険と考えれば、自分の収入全体をみてくれる収入保険は魅力的ですね。来年も継続加入するつもりです。
「保険料は収入安定のための必要経費」
【山形県高畠町 瀧澤 明大さん(40)】
(NOSAI山形広報紙「NOSAIやまがた」2019年9月号より)

栽培規模=水稲6ヘクタール、露地キュウリ30アール
収入保険の魅力は、野菜に対する補償があることですね。露地野菜は天候に左右されますし、相場が変動したり、家族の病気などで人手が減ると収入が変わります。少しでも収入が安定するようにと、多少掛捨て部分があっても「必要経費だ」と思って加入しました。車の任意保険と一緒で、加入していると安心です。
加入手続きは、国や県の助成金申請時も過去5年間の青色申告実績を提出したので慣れていますし、面倒ではなかったですね。私の場合は顔見知りの職員に説明や手続きに来てもらったので、話しやすくて全く心配なかったですよ。
私は掛金がいくらになるのか試算してもらい、その金額なら加入しようと決めました。まずは試算してもらうことをお勧めします。
「原木シイタケにはなかった保険」
【山形県三川町 石栗 聡さん(37)】
(NOSAI山形広報紙「NOSAIやまがた」2019年9月号より)

栽培規模=水稲6ヘクタール、原木シイタケ年植約18,000本
集落の集会で、NOSAIの職員から収入保険が始まると聞きました。原木シイタケを栽培している自分にとっては、今まで補償の無い分野だったので興味を持ちました。
原木シイタケ栽培は現在、原木の価格が非常に高騰していることもあり、榾木(ほだぎ)作りを一度失敗すると、翌年の再生産が極めて困難で、廃業に追い込まれる可能性があります。また、突発的な自然災害への不安もあったので、それらのリスクを回避するために加入しました。
同規模で、品質を保ちながら生産性を向上させる栽培方法には、リスクが伴います。収入保険の補償ができたことで、その栽培方法に取り組めるようになりました。
「加入する制度を一本化して簡潔に」
【宮城県大崎市 矢走 恵美子さん(45)】
(農業共済新聞[宮城県版]2019年8月1週号より抜すい)

主食用米20ヘクタール、飼料用米4.2ヘクタール、大豆14ヘクタール、施設野菜(青ネギ、ホウレンソウ)20アールを栽培しています。
近年発生する想定外の災害と、繁忙期の急な人員不足に不安を感じていました。家族がけがで圃場に出られなくなった際の、収入減少を補てんしてくれるのも心強いです。
品目ごとに加入する必要もないので、手続きをまとめられる点が魅力的ですね。収入保険の加入手続きには、主に青色申告で使用した税務書類を用いるので、大きな手間はありません。また、保険料や保険金も税務申告書類で計算するので分かりやすいと思います。
これからさらに経営面積を拡大し、従業員を雇用していくつもりなので、収入保険が安定した経営と従業員への給与の支払いを支えてくれると信じています。
「被災経験が決め手の一つ」
【北海道蘭越町 高張 直樹さん(40)、妻 みゆきさん(33)】
(農業共済新聞[北海道版]2019年7月1週号より抜すい)
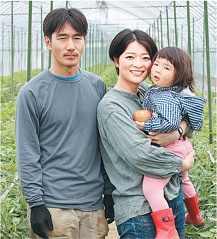
2017年4月に新規就農し、ハウス7棟で大玉トマトをメインに、ミニトマトと食用ホオズキを栽培しています。
就農した年に、農業改良普及センターの職員から「収入保険という制度が始まるので、そのために青色申告をしておいた方がいい」という話を聞き、青色申告を始めました。
新規就農者は、いろいろな作物を栽培する技術が未熟です。複数の作物でリスクを分散できるのが理想ですが、営農のメインであるトマトがだめだった場合が一番怖いですね。
就農した早々、春先の強風でビニールが破れ、パイプの一部が曲がる被害に遭い、就農2年目には、天候不順の影響で収量が減少しました。各地で発生する自然災害をはじめ、自分たちが被害を受けた経験もあり、迷わずに加入を決めました。
収入保険は保険料を分割で支払えることや、掛け捨てでない積み立て分もあるところに魅力を感じます。保険料も個人ごとの収入によって決まるのがいいですね。
「野菜の補償が必要」
【岩手県金ケ崎町 よこみちファーム株式会社 代表取締役 小原 伸一さん(64)】
( NOSAI岩手広報紙「結いの大地NOSAIいわて」2019年1月号より)

経営規模=水稲35.4ヘクタール/タマネギ2ヘクタール/アスパラガス80アールの他ミニトマトなど
水稲だけでなく、野菜も補償の対象になるということで収入保険への加入を決めました。
アスパラガスは金ケ崎町でも栽培が盛んです。アスパラガス、タマネギとも販売イベントに引き合いが強く、生産量が追いつかないこともあり、タマネギは栽培面積を2ヘクタールまで拡大しました。しかし、野菜価格安定基金の対象外の作物なので収入保険の必要性を感じました。
また、近年は突発的な集中豪雨も多いので、大雨などの水害や病虫害の発生も心配しています。農業生産で年間のキャッシュフローを考えると収入保険は欠かせないものだと考えています。
「カバーの範囲広く安心感」
【福島県福島市 まるせい果樹園 代表 佐藤 清一さん(49)】
(農業共済新聞2019年6月4週号より抜すい)

経営規模=サクランボやモモなど果樹7品目を栽培、果物狩り(6月~12月)・直売所・園内に設置したカフェを経営
収穫や管理作業のほかに、果物狩りなどの接客対応もあり、最大25人(うち通年雇用10人)が勤務しています。これだけの人数に遅滞なく給与を支払うには、安定した収入が欠かせません。
収入保険は、品目を問わず「けがや病気が原因で収穫できない」などカバーする減収要因の範囲が広いですね。当園が最も警戒している遅霜は、ひとたび被害を受けると損害額は百万円単位になります。昨年は遅霜のために例年の2、3割しか収穫できない品目もあり、被害の痛みを改めて実感しました。
最悪の事態になっても救いの道があるという安心感を得たことは、経営にとって大きなプラスになっています。
「自分の目指す経営にマッチ」
【北海道岩見沢市 (有)濱本農場 代表 濱本 壮男さん(42)】
(農業共済新聞[北海道版]2019年7月1週号より抜すい)

経営規模=水稲782アール/麦1,147アール/大豆519アール/カボチャ503アール
収入保険を知ったのは、いわみざわ地域・農業活性化連絡協議会で、農林水産省経営局保険課の講演を聞いたのがきっかけです。経営全体の収入の保険であり、保険金を受け取らなければ保険料が下がるという仕組みに好感を持ちました。何よりも収入保険があるから、新しいことにチャレンジできるということに魅力を感じますね。
天候による減収はもちろん、価格相場の変動にも対応する収入保険を選びました。トータルで見て農業共済よりも掛金が安くなり、自然災害のほか、あらゆるリスクを補償してくれる収入保険が自分の経営に合っていると判断しました。
「掛金も内容も魅力」
【秋田県由利本荘市 農事組合法人田高 代表理事 斎藤 善行さん(69)】
(農業共済新聞[秋田県版]2019年7月2週号より)

経営規模=水稲23.2ヘクタール/大豆14ヘクタール/タマネギ48.8アール/ミニトマト12アール/セリ6アール
法人は水稲と大豆がメインです。今よりも米価が下がると大変なので、タマネギやミニトマトなど多品目栽培に取り組んでおり、今年からセリも始めます。作業の効率化を図るため、耕地の集積を進めています。
法人は設立11年目で、青色申告を行っていたため、収入保険も選択肢の一つでした。組合で開いた説明会に参加し、収入保険と水稲共済・大豆共済との掛金比較シミュレーションをしてもらうなど、職員の方には熱心に対応していただきました。掛金の試算を割安に感じ、収入減少を補てんするという内容も魅力だったので加入しました。
昨年の水稲のように、収穫しないと分からない減収でも、収入保険であれば対応しているので安心です。
「NOSAIが窓口で心強い」
【青森県十和田市 小川 正孝さん(62)】
(農業共済新聞[青森県版] 2018年11月2週号より抜すい)

経営規模=水稲400アール/ゴボウ200アール/ダイコン150アール/ニンニク120アール
これまで、野菜の補償についてはNOSAIでの取り扱いがなく、品目ごとに野菜価格安定制度へ加入し、出荷した野菜の価格が保証基準額を下回ったときに助けられてきました。
収入保険は、価格低下や収量減少の他、さまざまな要因により収入が減少した場合にカバーする幅広い補償内容となっています。そこが、収入保険に加入した一番の理由です。また、品目の限定がないことも魅力です。
収入保険の説明会は何度も開催されましたので、数回足を運び、自分で納得してから加入する決断ができました。
加入に必要な書類の準備もNOSAI職員がフォローしてくれるので、農家にとって身近な存在であるNOSAIが窓口になったことはベストな選択だと思っています。
「病気や災害の備えに」
【青森県つがる市 三橋 弘さん(61)】
(農業共済新聞[青森県版] 2018年11月2週号より)

経営規模=水稲12.8ヘクタール/ブロッコリー1ヘクタール/大豆1ヘクタール
収入保険制度の説明会に何度か参加し、聞いているうちに、これは良い制度だと思いました。
私は、昨年6月に体を壊し入院生活を余儀なくされました。そのため、予定していた秋取りのブロッコリー栽培を断念せざるを得なくなり、その年の稲刈りは人を頼んでの収穫となりました。
そして今年、稲刈り前の収穫を予定してブロッコリーを植えましたが、長雨で定植時期が1週間もずれ込んでしまいました。そして追い打ちをかけるように、猛暑や3度の強風。結果、皆無作に近いものでした。
病気や自然災害には、なすすべもありません。そんなとき、安定した収入を得るには収入保険は心強く、必要な制度だと思います。
私はこれまでの苦しい経験上、収入保険の加入を決めました。大きな安心感が得られる収入保険の制度によって、後継者が増えることを強く期待しています。
「家族守るために選択」
【青森県弘前市 川村 公夫さん(56)】
(農業共済新聞[青森県版] 2018年11月2週号より)

経営規模=園芸施設でトマト40アール
収入保険の加入の決め手は、家族のためです。
収入保険は、自然災害や価格低下、病気やけがによるものなど農業収入の減少を幅広く補償対象としていて、さらに最高補償限度が9割となっているのは魅力的です。
近年、異常気象による自然災害が各地で猛威をふるい、大打撃を受けた農家も少なくないでしょう。そんなとき、われわれ農家を支えてくれるのが収入保険だと思っています。
私は幸いなことに、大病を患ったこともなく現在を迎えていますが、年を取り、病気やけがに気を付けなければならない年齢になっています。病気やけがで、長期間農作業ができない状況になった場合も補償してくれるのは大変助かります。
息子が後を継いでくれる幸運と、家族の幸せを守るために、私は収入保険に加入することを決意しました。
「けが、病気のときも補償がある安心感」
【宮城県東松島市 齋藤 英彦さん(56)】
(農業共済新聞[宮城県版] 2019年6月2週号より)

水稲10ヘクタールと、トウモロコシやハクサイのローテーション栽培20アールと、ナスなどの野菜苗を手掛けています。夫婦で栽培しているので、どちらかが予期せぬ病気にかかってしまうと、収穫量や収入の減少に大きく影響します。
病気やけがによる収入減少も補償の対象になるのは心強いですね。不意の事故で、営農が続けられなくなったときも、補償を受けられることで安心できます。
また、今まで指定野菜の補償制度はありましたが、対象外の品目については不安でした。これからは、全ての農産物を対象に、収入の減少分をカバーしてもらえるので、新しい野菜の品目に挑戦したいと思います。
今後、高齢化による離農農家からの受託作業が増えることを考えると、個人では限界があると感じています。将来的に、従業員を雇用することになった場合、安定して給与を支給できるよう、補償範囲が広い収入保険は心強いです。
「私は収入保険に決めました」
【北海道仁木町 勝浦 弘志さん】
(北海道NOSAI会報「NOSAI」2018年10月号より抜すい)
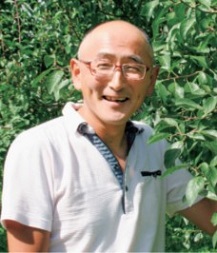
共済の対象外のサクランボを主体にリンゴ、プルーン、ミニトマトなどを栽培する複合経営を行っていますが、収入保険では、サクランボを含め全ての品目が補償の対象となることが一番のポイントです。
また、プルーンは本州の主産地の作柄により価格が大きく変動することがあり、ミニトマトも現在、価格は安定していますが、今後、産地間競争等による価格低下が心配です。その点、収入保険では、収量の減少だけでなく、価格の低下も補償してもらえるのは安心ですね。
さらに、国の補助もあり掛金が安いのも助かります。
最終的には、共済組合の職員さんからタブレットで果樹共済との比較など、わかりやすい説明をしてもらった結果、収入保険のほうがうちの経営にマッチしていると思ったので、加入を決めました。
「海外への輸出時の為替変動にも安心」
【宮城県大和町 赤間農業開発㈱代表取締役 赤間 良一さん(60)】
(農業共済新聞[宮城県版] 2019年6月2週号より抜すい)

「地域農業を支えたい」という一心で、2013年に会社を設立しました。
水稲は、主食用50ヘクタールと加工用を10ヘクタール、その他WCS用稲を3ヘクタール作付け。加工用米は甘酒生産に利用しています。
販路は主に農協や近隣のスーパーですが、最近は海外にも展開しています。
収入保険に加入を決めたのも、輸出時に、為替変動による、収入減少のリスクに備えたいと考えたからですね。
その他、昨年は3ヘクタールの田んぼが、イノシシによる被害を受けたように、獣害が年々増加していることも要因の一つです。保険の必要性を再認識しました。
販売する米は、専門機関が実施する成分分析でSランクを受けた良質米にこだわっているので、収入金額を基準に、収入が減少した際の補てん金が算定されるのは魅力的ですし、全ての農産物が対象となることもうれしいですね。
「台風で倒木被害 収量減に備えたい」
【宮城県亘理町 永谷 和彦さん(67)】
(農業共済新聞[宮城県版] 2019年6月2週号より)

水稲とリンゴを栽培。特にリンゴは、品種「ふじ」を中心に、早生から晩生まで20品種を手掛けています。
2018年10月に、台風24、25号が続けて襲来した際には、収穫前のリンゴ落果や、倒木といった深刻な被害を受けました。
樹体被害の場合は、翌年の着果にも影響するので、今年は例年通り収穫量を確保できるか心配でした。
今後、このような被害が発生しても、収入保険の最大補償割合を選択すれば、基準収入の9割を下回った場合も安心できますね。
加入時には、青色申告の実績から、保険料や収入が下がった場合の補てん金を、NOSAI職員がシミュレーションし、分かりやすく説明してくれました。果樹共済時代からの信頼関係が決め手になったと思います。
また、果樹は凍霜害・ひょう害など自然災害は避けられません。果樹農家や、小規模でも新しく挑戦する農家の方々に、経営の支えとなる収入保険をお勧めします。
「野菜分野の業務拡大へ」
【秋田県大仙市 農事組合法人たねっこ代表 工藤 修さん(67)】
(農業共済新聞 2019年5月2週号より抜すい)

経営規模=大仙市小種地域の5集落を集約し、約98%の農地で営農。主食用米約135ヘクタール、大豆約100ヘクタール、水稲の採種栽培、野菜約6ヘクタール(自社の野菜加工センターで冷凍野菜に加工し、販売)
2017年7月と8月に発生した記録的な大雨により、大豆の作付け面積の半分以上の約60ヘクタールの収穫が見込めない状況になりました。
農業共済と収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)に加入していましたが、同じような被害がまた発生したとき、野菜の生産・加工を含めた経営全体の収入減少を幅広く補償できる収入保険の方が魅力があると考え、収入保険に移行しました。
私たちの経営の場合は、基準収入が3億円を超えるため、保険料などの負担が不安でしたが、実際には、水稲共済や大豆共済の掛金、ナラシ対策の積立金を保険料などに充当でき、心配していたほどの負担感はありませんでした。
「品質低下の収入減も補償」
【岩手県一関市 小野 正一さん(68)】
(農業共済新聞 2019年事業推進特集号より)

経営規模=水稲26ヘクタール/小麦8ヘクタール
水稲の栽培面積26ヘクタールのうち、4ヘクタールで昨年市場デビューした県の新ブランド米「金色の風」を作付けています。今年は面積を拡大し、ブランド力を高めるためにも、品質の良い栽培を心がけています。
農業の多様化により、現行制度だけでは十分な補償を受けることが難しくなっていると感じています。収入保険制度は、ブランド米も生産者ごとの販売価格で補償されるのがメリットです。また、昨年のような天候不順の年には「くず米」が多くなり、販売収入の低下が心配されます。収入保険ではこれらもカバーされるので、期待しています。
保険金の支払いは青色申告後の審査となるので、現行制度より遅れることが想定されます。農業は先行投資の部分が大きいので、早期支払いが理想ですが、収入保険制度には「つなぎ融資」を活用できるとのことですので、農家は助かると思います。



